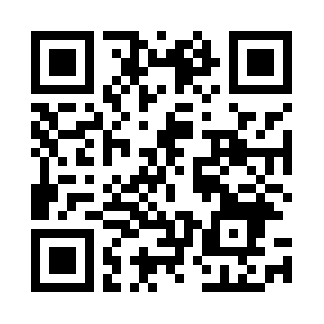第1部

開戦
旧幕軍と薩摩が”私闘”
時折風花が舞う中、ラッパの音が高らかに鳴り響き薩摩軍の小銃、大砲が一斉に火を噴いた。銃砲に装弾すらしていなかった旧幕府軍は虚を突かれ、砲弾の雨にさらされた。何とか反撃に転じるものの用意周到な新政府側に押され、次々と兵たちは倒れていった。
慶応4(1868)年1月3日午前、京を目指して鳥羽街道を北上していた旧幕軍は、洛南(らくなん)の上鳥羽村近く鴨川に架かった小枝橋付近(現・京都市南区と伏見区の境)で薩摩軍の足止めに遭った。新政府から上京命令を受けていた前将軍・徳川慶喜の先行隊で、「入京を許さずとは如何(いかが)の義にや」と主張した。だが、薩摩軍前線は許可の指示を受けておらず、「確認するまで待機せよ」と拒んだ。
押し問答は続き、いよいよ日が暮れる午後5時ごろ、しびれを切らした旧幕軍が「ぜひ罷(まか)り通る」と隊列を組み前進を強行。街道に展開していた薩摩軍は一斉に攻撃を仕掛け、「鳥羽・伏見の戦い」が幕を開けた。
慶応4(1868)年1月3日午前、京を目指して鳥羽街道を北上していた旧幕軍は、洛南(らくなん)の上鳥羽村近く鴨川に架かった小枝橋付近(現・京都市南区と伏見区の境)で薩摩軍の足止めに遭った。新政府から上京命令を受けていた前将軍・徳川慶喜の先行隊で、「入京を許さずとは如何(いかが)の義にや」と主張した。だが、薩摩軍前線は許可の指示を受けておらず、「確認するまで待機せよ」と拒んだ。
押し問答は続き、いよいよ日が暮れる午後5時ごろ、しびれを切らした旧幕軍が「ぜひ罷(まか)り通る」と隊列を組み前進を強行。街道に展開していた薩摩軍は一斉に攻撃を仕掛け、「鳥羽・伏見の戦い」が幕を開けた。
□ ■ □

鳥羽伏見地図
徳川幕府が正式に廃されたのは、前年12月9日の「王政復古」の政変だった。成立した新政府に慶喜の名前はなく、幼帝(明治天皇)を担ぎ“勝手”に振る舞う薩摩を旧幕府側は強く敵視した。
「薩摩討つべし」との声が日増しに強まる中、江戸市中をかく乱する浪士に手を焼いた庄内藩などが25日、薩摩藩邸を砲撃する事件を起こした。「江戸薩摩藩邸焼き打ち事件」の報は、対薩摩強硬派の会津・桑名の藩兵を燃え上がらせ、大坂城に退いていた慶喜には出陣要請が殺到した。
この時期の慶喜は「議定」として新政府入りがほぼ内定し、朝廷から上京要請を受けていた。慶喜は年が改まった元日に薩摩の罪状を上げ、「討薩の表」を発布、率兵上京を決めた。
敵対する薩摩藩在京首脳部も好機とみた。江戸市中かく乱は、元はと言えば「武力衝突」を前提として西郷隆盛らが授けた作戦。新政府に残ろうともくろむ慶喜に対し、危機感を強める大久保利通は「戦に及ばず候(そうら)えば、皇国の事はそれきり水泡と相成り」と武力排除の機会を探っており、この「討薩の表」で名目を得た。
西郷も詳細な戦争計画を練った。敗れた場合には、天皇を山陰地方に避難させるといった算段も付けていた。黎明館の市村哲二学芸専門員(46)は「薩摩側にとって、軍事衝突は起死回生の機会。まさに両者の覇権争いとなった」とみる。
「薩摩討つべし」との声が日増しに強まる中、江戸市中をかく乱する浪士に手を焼いた庄内藩などが25日、薩摩藩邸を砲撃する事件を起こした。「江戸薩摩藩邸焼き打ち事件」の報は、対薩摩強硬派の会津・桑名の藩兵を燃え上がらせ、大坂城に退いていた慶喜には出陣要請が殺到した。
この時期の慶喜は「議定」として新政府入りがほぼ内定し、朝廷から上京要請を受けていた。慶喜は年が改まった元日に薩摩の罪状を上げ、「討薩の表」を発布、率兵上京を決めた。
敵対する薩摩藩在京首脳部も好機とみた。江戸市中かく乱は、元はと言えば「武力衝突」を前提として西郷隆盛らが授けた作戦。新政府に残ろうともくろむ慶喜に対し、危機感を強める大久保利通は「戦に及ばず候(そうら)えば、皇国の事はそれきり水泡と相成り」と武力排除の機会を探っており、この「討薩の表」で名目を得た。
西郷も詳細な戦争計画を練った。敗れた場合には、天皇を山陰地方に避難させるといった算段も付けていた。黎明館の市村哲二学芸専門員(46)は「薩摩側にとって、軍事衝突は起死回生の機会。まさに両者の覇権争いとなった」とみる。
□ ■ □
旗本に会津・桑名の藩兵を加え大坂城を出た旧幕軍は約1万人。1月3日、鳥羽と伏見の両街道から京を目指した。伏見では奉行所に陣取った旧幕軍に対し、薩摩と長州に一部の土佐兵を加えた軍が囲み、鳥羽方面から聞こえてきた砲声に合わせて戦端が開かれた。
奉行所を守っていたのは会津兵や新選組で士気は高かったが、刀や槍(やり)が中心の部隊だった。薩摩側にたびたび突撃を試みたが、激しい銃砲撃に押し返された。戦闘も市街地に広がり、一帯は焦土と化した。
朝廷からは薩長土に市中警護の命が降ったが、土佐藩は積極的に戦闘に参加しなかった。前藩主・山内容堂から「戦いは旧幕と薩長による『私闘』のため中立の立場を取るよう」厳命されていたからだった。
新政府内部でも対応を巡り、戦闘を主張する薩摩などに対し、容堂や前越前藩主・松平春嶽らが公議を尽くすべきと訴え、薩長の“独断専行”をけん制した。3日時点では多くの藩も様子見を決め込み、「私闘」との見方が大勢を占めていた。
奉行所を守っていたのは会津兵や新選組で士気は高かったが、刀や槍(やり)が中心の部隊だった。薩摩側にたびたび突撃を試みたが、激しい銃砲撃に押し返された。戦闘も市街地に広がり、一帯は焦土と化した。
朝廷からは薩長土に市中警護の命が降ったが、土佐藩は積極的に戦闘に参加しなかった。前藩主・山内容堂から「戦いは旧幕と薩長による『私闘』のため中立の立場を取るよう」厳命されていたからだった。
新政府内部でも対応を巡り、戦闘を主張する薩摩などに対し、容堂や前越前藩主・松平春嶽らが公議を尽くすべきと訴え、薩長の“独断専行”をけん制した。3日時点では多くの藩も様子見を決め込み、「私闘」との見方が大勢を占めていた。