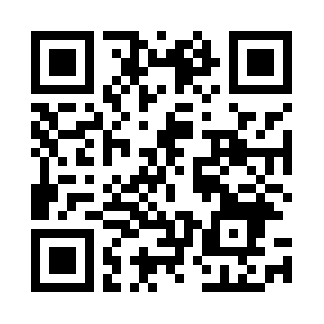第10部

女学校創立
理想を追求し私学続々
赤坂仮皇居隣に設けられた華族女学校、その開校式に22歳になった津田梅子は新しい金色のドレスで臨んだ。米国留学から帰国して3年、教授補としてようやくその使命を果たせると高揚していた。明治18(1885)年10月13日のことだった。
式典には創設準備委員となった伯爵夫人・大山捨松の姿もあった。前年、伊藤博文に就任を求められ、講義科目などを助言していた。米国の大学の学位を持つ女性は当時、ほかにいなかった。親友アリス・ベーコンへの手紙には「生涯の夢が実現しようとしている」と喜びをつづった。
だが、それは失望へと変わった。「他家に嫁して夫に仕えるのだから」「家を治めるのに化学理学は役に立たない」などと教育内容を男子と区別するよう指示され、生徒心得には「夫に配しては良妻たるべく、子を得ては賢母たるべく」とあった。
中心の教授(後に学監)は元宮中女官の下田歌子。幼い頃から儒学に親しみ、和歌の才で知られた。上流階級に教養を伝える「桃夭(とうよう)女塾(じょじゅく)」を開いており、そこでは梅子も英語を教えたことがあったが、方向性は異なっていた。
教壇の梅子は危機感を抱いた。貞淑や従順が美徳と教えられてきた少女には、自分自身の意見や向上心すら持たない者が少なくなかった。一生、精神的にも経済的にも親、夫、子など周囲に依存し続けるしかないではないか-。梅子は、自立した女性を育てる学校づくりの夢を新たにした。
式典には創設準備委員となった伯爵夫人・大山捨松の姿もあった。前年、伊藤博文に就任を求められ、講義科目などを助言していた。米国の大学の学位を持つ女性は当時、ほかにいなかった。親友アリス・ベーコンへの手紙には「生涯の夢が実現しようとしている」と喜びをつづった。
だが、それは失望へと変わった。「他家に嫁して夫に仕えるのだから」「家を治めるのに化学理学は役に立たない」などと教育内容を男子と区別するよう指示され、生徒心得には「夫に配しては良妻たるべく、子を得ては賢母たるべく」とあった。
中心の教授(後に学監)は元宮中女官の下田歌子。幼い頃から儒学に親しみ、和歌の才で知られた。上流階級に教養を伝える「桃夭(とうよう)女塾(じょじゅく)」を開いており、そこでは梅子も英語を教えたことがあったが、方向性は異なっていた。
教壇の梅子は危機感を抱いた。貞淑や従順が美徳と教えられてきた少女には、自分自身の意見や向上心すら持たない者が少なくなかった。一生、精神的にも経済的にも親、夫、子など周囲に依存し続けるしかないではないか-。梅子は、自立した女性を育てる学校づくりの夢を新たにした。
□ ■ □
梅子は明治22年、復職を条件に再留学を許された。最初の留学の際は数えで8歳、あまりに幼く、大学までは進めなかった。渡米2回目は、新設されたブリンマー大学に授業料免除の特待生として入学した。
華族女学校では不用とされた生物学を専攻。1年延長して師範学校にも学び、後進の留学にも道をつけた。知人たちに協力を呼び掛け、1年間で8000ドルを集めて基金「ジャパニーズ・スカラシップ」を設立。梅子が帰国した明治25年から80年余にわたり、25人が同大などで学んだ。
津田塾大学の高橋裕子学長=アメリカ社会史=は「女子留学生が、点ではなく線となって続くことを願った。成果を次代に受け継ぎ、社会にインパクトを与えることが、梅子の建学精神の源流にあった」と語る。
念願の学校設立のため、華族女学校と兼任していた東京女子師範学校を辞職したのは明治33(1900)年。前年の高等女学校令で各府県に高等女学校設置が求められた。
翌34年、梅子は東京麹町の借家に女子英学塾を開いた。捨松は後援者となり、アリス・ベーコンらも来日して教師を務めた。梅子は「真の教育は生徒の個性に従って行われるべき」と語りかけた。英語以外の科目も教え、討論を行って自分の意見を持つよう促すなど、自立した女性を育てるとの理想を追求した。
華族女学校では不用とされた生物学を専攻。1年延長して師範学校にも学び、後進の留学にも道をつけた。知人たちに協力を呼び掛け、1年間で8000ドルを集めて基金「ジャパニーズ・スカラシップ」を設立。梅子が帰国した明治25年から80年余にわたり、25人が同大などで学んだ。
津田塾大学の高橋裕子学長=アメリカ社会史=は「女子留学生が、点ではなく線となって続くことを願った。成果を次代に受け継ぎ、社会にインパクトを与えることが、梅子の建学精神の源流にあった」と語る。
念願の学校設立のため、華族女学校と兼任していた東京女子師範学校を辞職したのは明治33(1900)年。前年の高等女学校令で各府県に高等女学校設置が求められた。
翌34年、梅子は東京麹町の借家に女子英学塾を開いた。捨松は後援者となり、アリス・ベーコンらも来日して教師を務めた。梅子は「真の教育は生徒の個性に従って行われるべき」と語りかけた。英語以外の科目も教え、討論を行って自分の意見を持つよう促すなど、自立した女性を育てるとの理想を追求した。
□ ■ □
女子教育推進のため政府は明治5(1872)年に東京女学校、同8年には教師を育てる女子師範学校を開き、地方の府県も次々に女学校を設けた。鹿児島では翌9年の鹿児島女子師範学校が最初だった。
女学校は「女紅場(にょこうば)」とも呼ばれ、英語や習字、算術、裁縫、手芸など多様な科目を教えた。後に女紅場は勧業授産、女学校は才芸知識の開達のためと、区別されるようになった。
私学の開設も続いた。京都に同志社英学塾を開いた新島襄は、男子と対になる女子の教育機関として明治10年、同志社分校女紅場(のち女学校)を開いた。新島の妻八重は捨松と同じ会津出身だった。同32年には下田歌子の実践女学校、34年には日本女子大学校と開設は相次いだ。同志社はじめキリスト教団体や宣教師が設立に関わった女学校は少なくない。「神の前では男女は対等」とするキリスト教的価値観に基づいた教育が行われるようになった。
古き良き「良妻賢母」だけでなく、新たな価値観のもとで女性像は広がりをみせていった。
女学校は「女紅場(にょこうば)」とも呼ばれ、英語や習字、算術、裁縫、手芸など多様な科目を教えた。後に女紅場は勧業授産、女学校は才芸知識の開達のためと、区別されるようになった。
私学の開設も続いた。京都に同志社英学塾を開いた新島襄は、男子と対になる女子の教育機関として明治10年、同志社分校女紅場(のち女学校)を開いた。新島の妻八重は捨松と同じ会津出身だった。同32年には下田歌子の実践女学校、34年には日本女子大学校と開設は相次いだ。同志社はじめキリスト教団体や宣教師が設立に関わった女学校は少なくない。「神の前では男女は対等」とするキリスト教的価値観に基づいた教育が行われるようになった。
古き良き「良妻賢母」だけでなく、新たな価値観のもとで女性像は広がりをみせていった。