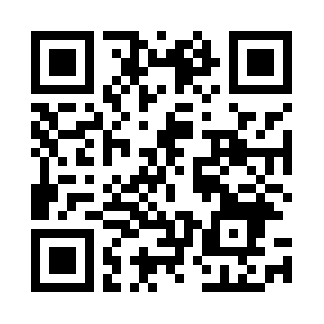第12部

巨星墜つ
九州を転戦、薩軍が敗北
雨は降る降る人馬は濡(ぬ)れる、越すに越されぬ田原坂―。民謡「田原坂(豪傑節)」に謡われたように、敵味方入り乱れた白兵戦は、降りしきる雨の中だった。
明治10(1877)年3月4日、最大の激戦となった「田原坂の戦い」が始まった。樹木が茂り大雨で視界も遮られる中、田原坂(熊本市)の丘上などに陣取る薩軍(西郷軍)を攻撃しようと、政府軍は坂を上ろうとして痛撃を受けた。
鎮台兵の籠城する熊本城を救うため南下してきた政府軍を阻止すべく、薩軍は砲隊も通ることができる主要道、田原坂を防御線として陣を敷いた。高さ約80メートルの緩やかな丘陵だが、道が斜面に囲まれ攻撃を受けやすい地形だった。
「銃撃は雨霰(あられ)のようで、前進する官軍兵は必ず傷つき、退くものは必ず倒れた」。連日続いた戦闘では、日に銃弾が数十万発飛び交い、双方の弾がかち合うほどの乱戦となった。両軍ともに疲労は濃く、弾薬が欠乏し、至る所で白兵戦にもなった。薩軍は士族中心で、刀を持っての白兵戦は望むところ。徴兵制の兵中心の政府軍は苦戦、苦肉の策として旧会津藩など士族出身の警察官を「警視抜刀隊」として緊急編成。戦場では「戊辰の復讐(ふくしゅう)」といった声もこだました。
17日間にわたる激闘は、物量に勝る政府軍が辛勝した。一方、別部隊「衝背軍」は海路で日奈久(八代市)に3月19日上陸。熊本南部をおさえた政府軍は、薩軍の鹿児島からの補給路を遮断し、撤退に追い込んだ。
薩軍は政府軍に比べ、武器が旧式とされているが、近年の発掘調査では相当数の新式を使っていたことも判明している。熊本博物館の中原幹彦学芸員(61)は「薩軍は、少なくとも田原坂の頃までは、武器の性能では見劣りしていなかった」と言う。
明治10(1877)年3月4日、最大の激戦となった「田原坂の戦い」が始まった。樹木が茂り大雨で視界も遮られる中、田原坂(熊本市)の丘上などに陣取る薩軍(西郷軍)を攻撃しようと、政府軍は坂を上ろうとして痛撃を受けた。
鎮台兵の籠城する熊本城を救うため南下してきた政府軍を阻止すべく、薩軍は砲隊も通ることができる主要道、田原坂を防御線として陣を敷いた。高さ約80メートルの緩やかな丘陵だが、道が斜面に囲まれ攻撃を受けやすい地形だった。
「銃撃は雨霰(あられ)のようで、前進する官軍兵は必ず傷つき、退くものは必ず倒れた」。連日続いた戦闘では、日に銃弾が数十万発飛び交い、双方の弾がかち合うほどの乱戦となった。両軍ともに疲労は濃く、弾薬が欠乏し、至る所で白兵戦にもなった。薩軍は士族中心で、刀を持っての白兵戦は望むところ。徴兵制の兵中心の政府軍は苦戦、苦肉の策として旧会津藩など士族出身の警察官を「警視抜刀隊」として緊急編成。戦場では「戊辰の復讐(ふくしゅう)」といった声もこだました。
17日間にわたる激闘は、物量に勝る政府軍が辛勝した。一方、別部隊「衝背軍」は海路で日奈久(八代市)に3月19日上陸。熊本南部をおさえた政府軍は、薩軍の鹿児島からの補給路を遮断し、撤退に追い込んだ。
薩軍は政府軍に比べ、武器が旧式とされているが、近年の発掘調査では相当数の新式を使っていたことも判明している。熊本博物館の中原幹彦学芸員(61)は「薩軍は、少なくとも田原坂の頃までは、武器の性能では見劣りしていなかった」と言う。
□ ■ □
3月下旬にもなると、国内各地から政府軍の援軍が続々と戦場に到着、圧倒的な兵力と物量で薩軍を追い込んでいった。
田原坂以降、薩軍にとって戦局は悪化の一途をたどった。4月14日には政府軍一隊の熊本城下進行を許し、2カ月近くにわたる包囲を解いた。薩軍は20日、「城東会戦」で敗北、本営が浜町(山都町)に後退した。
薩軍幹部は翌21日の軍議で、人吉に移り劣勢挽回を図ることを決定した。すでに大隊長の篠原国幹と永山弥一郎のほか、西郷隆盛の末弟・小兵衛らも戦死し、被害は甚大だった。
政府軍側は追撃の手を緩めず、6月1日に人吉を陥落させ、西郷らは宮崎で転戦する道を選んだ。この時期になると、薩軍の中には戦意喪失で集団投降する者も現れ始めていた。
手薄だった鹿児島には、3月8日に海軍に護衛された勅使・柳原前光が入り、薩軍に協力的な県令・大山綱良を拘束。滝ノ上火薬製造所なども破壊して一度退去するが、4月上陸軍により城下が占拠された。
熊本から宮崎に入った薩軍本隊は、各地を転戦しながら延岡に達した。別行動を取り、大分近郊にまで達していた野村忍介率いる「奇兵隊」と合流。8月15日、延岡奪還をかけ最後の総攻撃をしかけた。
初めて陣頭指揮を執った西郷だったが、結局敗れ、近くの長井村(延岡市)で16日、軍の解散を指示。2日後、政府軍が囲む可愛岳(えのだけ)を突破し、故郷・鹿児島へ向けひたすら逃避行を続けた。
田原坂以降、薩軍にとって戦局は悪化の一途をたどった。4月14日には政府軍一隊の熊本城下進行を許し、2カ月近くにわたる包囲を解いた。薩軍は20日、「城東会戦」で敗北、本営が浜町(山都町)に後退した。
薩軍幹部は翌21日の軍議で、人吉に移り劣勢挽回を図ることを決定した。すでに大隊長の篠原国幹と永山弥一郎のほか、西郷隆盛の末弟・小兵衛らも戦死し、被害は甚大だった。
政府軍側は追撃の手を緩めず、6月1日に人吉を陥落させ、西郷らは宮崎で転戦する道を選んだ。この時期になると、薩軍の中には戦意喪失で集団投降する者も現れ始めていた。
手薄だった鹿児島には、3月8日に海軍に護衛された勅使・柳原前光が入り、薩軍に協力的な県令・大山綱良を拘束。滝ノ上火薬製造所なども破壊して一度退去するが、4月上陸軍により城下が占拠された。
熊本から宮崎に入った薩軍本隊は、各地を転戦しながら延岡に達した。別行動を取り、大分近郊にまで達していた野村忍介率いる「奇兵隊」と合流。8月15日、延岡奪還をかけ最後の総攻撃をしかけた。
初めて陣頭指揮を執った西郷だったが、結局敗れ、近くの長井村(延岡市)で16日、軍の解散を指示。2日後、政府軍が囲む可愛岳(えのだけ)を突破し、故郷・鹿児島へ向けひたすら逃避行を続けた。
□ ■ □

西郷隆盛が最期を迎えた地に立つ「南洲翁終焉之地」碑=鹿児島市城山町
9月1日、鹿児島に西郷一行はたどり着いた。城山に立てこもったのは桐野利秋や別府晋介ら、わずか372人だった。
城山は政府軍に包囲され、連日砲撃を浴びた。24日午前4時、山県有朋を司令官とする政府軍は総攻撃をしかけた。同7時ごろ、城山洞窟を出た西郷らは敵陣に向かって前進した。
岩崎谷を下ったところ、一発の銃弾が西郷の太ももに命中し、歩くことができなくなった。「晋どん、もうここでよかろう」。西郷はそう口にした(「西南記伝」)。明治天皇のいる東の方角を仰いで西郷が自決、ついに“巨星”は墜(お)ちた。
城山は政府軍に包囲され、連日砲撃を浴びた。24日午前4時、山県有朋を司令官とする政府軍は総攻撃をしかけた。同7時ごろ、城山洞窟を出た西郷らは敵陣に向かって前進した。
岩崎谷を下ったところ、一発の銃弾が西郷の太ももに命中し、歩くことができなくなった。「晋どん、もうここでよかろう」。西郷はそう口にした(「西南記伝」)。明治天皇のいる東の方角を仰いで西郷が自決、ついに“巨星”は墜(お)ちた。