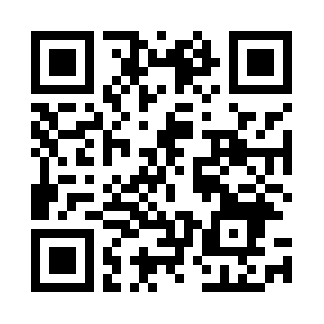第2部

天皇の公使謁見
「諸国と対等」準備整う
満15歳の明治天皇は、即位の礼など主な朝廷行事がある紫宸殿(ししんでん)に現れた。烏帽子(えぼし)をかぶった引直衣(ひきのうし)姿。駐日外国公使らの敬礼に立ち上がって応えた。眉をそり、ほおに紅、唇は赤く塗り、お歯黒に染めていた。左右に議定の山階(やましな)宮晃親王、参与の岩倉具視らが控えた。「両国の交際が親密を深め、永久不変となることを望む」-。ささやくような声を山階宮が声高に伝え、伊藤博文が通訳した。
慶応4(1868)年2月30日、天皇は外国公使を初めて謁見(えっけん)した。相手は仏・ロッシュ、オランダ・ポルスブルックだった。
同日予定されていた英・パークスは浪士による襲撃事件によって延期され、3月3日に行われた。英公使と同席した書記官ミットフォードらの回想などによれば簡素な大広間。中央に漆塗りの柱で支えられた天蓋(てんがい)があり、模様入りの白い絹の御簾(みす)で覆われていた。
述べた言葉はほぼ同じだったが、パークスには事件への「遺憾」の意と、引見の喜びが加えられた。綿密に段取られた儀礼は15分足らず。ミットフォードは「突然に神殿のベールは引き裂かれ、現人神(あらひとがみ)の少年が雲から降りて来て、人間の子と同じ席に着いた。その尊い顔を人の目に触れさせ、『外夷(がいい)』と親交を結んだ」と記した。
一方、旧幕府と関係が深かったロッシュは「その風貌は、知性の一片の痕跡をも示していない」と評した(石井孝「増訂明治維新の国際的環境」)。
慶応4(1868)年2月30日、天皇は外国公使を初めて謁見(えっけん)した。相手は仏・ロッシュ、オランダ・ポルスブルックだった。
同日予定されていた英・パークスは浪士による襲撃事件によって延期され、3月3日に行われた。英公使と同席した書記官ミットフォードらの回想などによれば簡素な大広間。中央に漆塗りの柱で支えられた天蓋(てんがい)があり、模様入りの白い絹の御簾(みす)で覆われていた。
述べた言葉はほぼ同じだったが、パークスには事件への「遺憾」の意と、引見の喜びが加えられた。綿密に段取られた儀礼は15分足らず。ミットフォードは「突然に神殿のベールは引き裂かれ、現人神(あらひとがみ)の少年が雲から降りて来て、人間の子と同じ席に着いた。その尊い顔を人の目に触れさせ、『外夷(がいい)』と親交を結んだ」と記した。
一方、旧幕府と関係が深かったロッシュは「その風貌は、知性の一片の痕跡をも示していない」と評した(石井孝「増訂明治維新の国際的環境」)。
□ ■ □
「天皇が外国公使を直接謁見することが必要」。英国公使館書記官アーネスト・サトウは、王政復古直後の慶応3(67)年12月末、参与の大久保利通の意向を受け、大坂を訪れた薩摩藩きっての外国通、寺島宗則にこう助言した。「新政府を諸外国に認めさせるにはどうすればいいか」との質問に対する答えだった(青山忠正「明治維新の言語と史料」)。
サトウの提案を踏まえ、翌年2月7日、松平春嶽、山内容堂、島津忠義ら武家議定6人は連署で、外国人を忌み嫌う風習を改め「(天皇自ら)万国普通之公法を以(も)って参朝をも命ぜられ候様(そうろうよう)、御賛成あらさせられ」と外国公使の参内謁見と、その旨を一般に広く知らせるよう求める建言書を出し、新政府は布告した。
先帝・孝明天皇が文久3(63)年、攘夷(じょうい)祈願のため賀茂社と岩清水八幡宮に行幸するまで237年間、歴代天皇は京都御所から出たことがなかった。その姿は宮中奥深くにあり、民衆の日常生活には無関係だった。公家が雲上人として祭り上げてきた結果だった。新政府が天皇親政を宣言した以上、「見える天皇」となり、西洋並みに君主たることを示すことを迫られた。
サトウの提案を踏まえ、翌年2月7日、松平春嶽、山内容堂、島津忠義ら武家議定6人は連署で、外国人を忌み嫌う風習を改め「(天皇自ら)万国普通之公法を以(も)って参朝をも命ぜられ候様(そうろうよう)、御賛成あらさせられ」と外国公使の参内謁見と、その旨を一般に広く知らせるよう求める建言書を出し、新政府は布告した。
先帝・孝明天皇が文久3(63)年、攘夷(じょうい)祈願のため賀茂社と岩清水八幡宮に行幸するまで237年間、歴代天皇は京都御所から出たことがなかった。その姿は宮中奥深くにあり、民衆の日常生活には無関係だった。公家が雲上人として祭り上げてきた結果だった。新政府が天皇親政を宣言した以上、「見える天皇」となり、西洋並みに君主たることを示すことを迫られた。
□ ■ □
謁見に先立ち、朝廷内では反対論が渦巻いた。
参与だった東久世通禧(みちとみ)の回顧録では当時は公卿(くぎょう)から庶民まで外国人を「禽獣(きんじゅう)半分人間半分」のように考えていて、公使との握手に関して「わが国の臣下にさえ手を握らないのに、天照皇太神宮に申し訳ない」と訴える者もいた。
天皇の祖父の中山忠能(ただやす)は前夜、天皇は侍医の診断で微熱があるとして延期を申し入れた。だが、岩倉は別の医師から「大丈夫」とのお墨付きを得て強行した。
国際日本文化研究センター(京都市)のジョン・ブリーン教授(61)=日本近代史=は「朝廷の反対は、謁見によって天皇が開国和親を掲げる新政府の象徴になるという重要性を熟知していたからだ」と指摘。日本が主権国家になる条件は「万国公法を受け入れ、公法が定める文明国家になることだった。その過程で天皇のあり方も文明化を求められた」と語る。
謁見儀式は欧州の宮廷と近い形で行われた。諸外国による事実上の天皇政府(新政府)承認だった。ミットフォードは「日本は国際礼譲の場へ諸国と対等の条件で入る準備が整った」とその画期性を書きとめた。
参与だった東久世通禧(みちとみ)の回顧録では当時は公卿(くぎょう)から庶民まで外国人を「禽獣(きんじゅう)半分人間半分」のように考えていて、公使との握手に関して「わが国の臣下にさえ手を握らないのに、天照皇太神宮に申し訳ない」と訴える者もいた。
天皇の祖父の中山忠能(ただやす)は前夜、天皇は侍医の診断で微熱があるとして延期を申し入れた。だが、岩倉は別の医師から「大丈夫」とのお墨付きを得て強行した。
国際日本文化研究センター(京都市)のジョン・ブリーン教授(61)=日本近代史=は「朝廷の反対は、謁見によって天皇が開国和親を掲げる新政府の象徴になるという重要性を熟知していたからだ」と指摘。日本が主権国家になる条件は「万国公法を受け入れ、公法が定める文明国家になることだった。その過程で天皇のあり方も文明化を求められた」と語る。
謁見儀式は欧州の宮廷と近い形で行われた。諸外国による事実上の天皇政府(新政府)承認だった。ミットフォードは「日本は国際礼譲の場へ諸国と対等の条件で入る準備が整った」とその画期性を書きとめた。