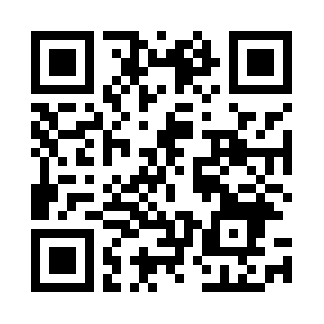第7部

国民啓蒙
「明六社」雑誌作り喚起
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」―。明治5(1872)年2月、明治期最大の啓蒙(けいもう)思想家、福沢諭吉は「学問のすゝめ」を刊行した。
実学の重要性や国民皆学の思想を鼓舞する内容だった。「人は生れながらにして貴賤(きせん)貧富の別なし。ただ学問を勤めて物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人となる」。人間の平等を強調し、学問を修めて独立した個人を養うことで独立した国家の建設を目指すと説いた。
四民平等の時代になったが、当時は帯刀など武士の特権は残り、市井の人々にはまだ江戸時代の身分制度が染みついていた。欧米への渡航経験が豊富な福沢の言葉は、学問が道を開く新時代の到来を感じさせたに違いない。
小学校の教科書となることを見越し、教育を受けていない人など幅広い層にも理解されるよう平易な文章で書かれたのも万民受けした。明治9年までに計17編刊行し、毎号20万冊以上売れた(会田倉吉「福沢諭吉」)。累計約340万冊となる計算で、当時の人口約3300万人(明治5~6年、壬申戸籍)とすると、10人に1人が読んだという大ベストセラー。開化史に大きな影響を及ぼした。
実学の重要性や国民皆学の思想を鼓舞する内容だった。「人は生れながらにして貴賤(きせん)貧富の別なし。ただ学問を勤めて物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人となる」。人間の平等を強調し、学問を修めて独立した個人を養うことで独立した国家の建設を目指すと説いた。
四民平等の時代になったが、当時は帯刀など武士の特権は残り、市井の人々にはまだ江戸時代の身分制度が染みついていた。欧米への渡航経験が豊富な福沢の言葉は、学問が道を開く新時代の到来を感じさせたに違いない。
小学校の教科書となることを見越し、教育を受けていない人など幅広い層にも理解されるよう平易な文章で書かれたのも万民受けした。明治9年までに計17編刊行し、毎号20万冊以上売れた(会田倉吉「福沢諭吉」)。累計約340万冊となる計算で、当時の人口約3300万人(明治5~6年、壬申戸籍)とすると、10人に1人が読んだという大ベストセラー。開化史に大きな影響を及ぼした。
□ ■ □
「福諭(福沢諭吉)、西周等の諸家その任に如何(いかん)」。国家発展の基本は新たな教育制度の確立と考えていた森有礼は明治4年、欧米での現地視察の必要性を訴え、派遣する有力候補として2人の名前を挙げた。
明治6年、米国から帰国した森は、福沢らとともに日本初の啓蒙思想団体「明六社」を立ち上げた。米国で“学会”を組織し、学術研究している学者らが雑誌発表や講演を通し、民衆の教育を率先している姿を目の当たりにしたからだ。
「我国の教育を進めんがために有志の徒会同して、その手段を商議するにあり。また、同志集会して異見を交換し、知を広め識を明にするにあり」。設立の趣旨にはこう記し、社長には森が就いた。
翌明治7年4月「明六雑誌」を刊行。明六社での論議の内容を雑誌で公開し、世論を喚起して国民啓蒙を推進する狙いだった。
学術雑誌の先駆けとして、その取り上げるテーマは政治や法律、外交、財政、哲学など多岐にわたった。毎月2、3冊のペースで平均20ページほどで発行した。若い知識人たちが競って買い求め、毎号平均3200部、年間で8万冊超も売れたという。同年秋には、西洋流の演説会が催されるようになった。新聞広告で聴衆を募集し、毎回大入りという好評ぶりだった。
女子啓蒙にも力を入れた。森は「妻妾(さいしょう)論」、福沢は「男女同数論」をそれぞれ明六雑誌で発表し、男女同権論を展開。女子教育の普及や地位向上を促した。
東京開成学校(東京大学の前身)初代校長となった畠山義成や、洋学者で後に和仏法律学校(法政大学の前身)の校長となる箕作麟祥(みつくりりんしょう)らが集い、名実共に啓発の旗手となった。
明治6年、米国から帰国した森は、福沢らとともに日本初の啓蒙思想団体「明六社」を立ち上げた。米国で“学会”を組織し、学術研究している学者らが雑誌発表や講演を通し、民衆の教育を率先している姿を目の当たりにしたからだ。
「我国の教育を進めんがために有志の徒会同して、その手段を商議するにあり。また、同志集会して異見を交換し、知を広め識を明にするにあり」。設立の趣旨にはこう記し、社長には森が就いた。
翌明治7年4月「明六雑誌」を刊行。明六社での論議の内容を雑誌で公開し、世論を喚起して国民啓蒙を推進する狙いだった。
学術雑誌の先駆けとして、その取り上げるテーマは政治や法律、外交、財政、哲学など多岐にわたった。毎月2、3冊のペースで平均20ページほどで発行した。若い知識人たちが競って買い求め、毎号平均3200部、年間で8万冊超も売れたという。同年秋には、西洋流の演説会が催されるようになった。新聞広告で聴衆を募集し、毎回大入りという好評ぶりだった。
女子啓蒙にも力を入れた。森は「妻妾(さいしょう)論」、福沢は「男女同数論」をそれぞれ明六雑誌で発表し、男女同権論を展開。女子教育の普及や地位向上を促した。
東京開成学校(東京大学の前身)初代校長となった畠山義成や、洋学者で後に和仏法律学校(法政大学の前身)の校長となる箕作麟祥(みつくりりんしょう)らが集い、名実共に啓発の旗手となった。
□ ■ □
明治8年6月、明六社に転機が訪れた。自由民権運動に警戒していた政府が、「新聞紙条例」「讒謗律(ざんぼうりつ)」を制定し、言論統制を強化したのだ。
「民撰議院」論争など政治、社会について論じていた明六雑誌も法に触れることが懸念された。福沢は自由な議論ができなくなると考え、雑誌廃刊を提案。高い理想を掲げる森は反対したがかなわず、明六社の活動も停止した。森は「明六(あけむつ)の幽霊」と明六社と有礼を“ゆうれい”の読みにかけて揶揄(やゆ)され、突出ぶりが反感を集めてもいた。
森と福沢は違う意見を発表し合うなど、互いの立場で教育を考え、個性がぶつかることも少なくなかった。慶応義塾大学の山本正身教授は「学会をつくり、知識人たちがリードして、教育で国を富ませるということは共通していた」とした上で、「国が先頭になって教育に取り組むという立場の森と、個人の知徳の向上が国を強くすると考えた福沢。教育へのアプローチの図式は異なっていた」と解説する。
明六社の流れは、その後福沢や西、津田真道らに受け継がれ、帝国学士院などを経て日本学士院へと至ることとなった。
「民撰議院」論争など政治、社会について論じていた明六雑誌も法に触れることが懸念された。福沢は自由な議論ができなくなると考え、雑誌廃刊を提案。高い理想を掲げる森は反対したがかなわず、明六社の活動も停止した。森は「明六(あけむつ)の幽霊」と明六社と有礼を“ゆうれい”の読みにかけて揶揄(やゆ)され、突出ぶりが反感を集めてもいた。
森と福沢は違う意見を発表し合うなど、互いの立場で教育を考え、個性がぶつかることも少なくなかった。慶応義塾大学の山本正身教授は「学会をつくり、知識人たちがリードして、教育で国を富ませるということは共通していた」とした上で、「国が先頭になって教育に取り組むという立場の森と、個人の知徳の向上が国を強くすると考えた福沢。教育へのアプローチの図式は異なっていた」と解説する。
明六社の流れは、その後福沢や西、津田真道らに受け継がれ、帝国学士院などを経て日本学士院へと至ることとなった。