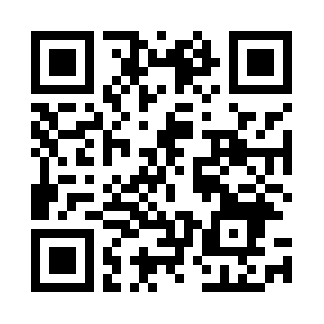第12部

プロローグ
薩軍蜂起
高く反り返った石垣「武者返し」が幾重に連なる姿からも、城が堅固なことは言わずもがなだった。築城の名手・加藤清正が江戸初期に完成させた熊本城。西郷軍(薩軍)にとって、熊本鎮台が置かれていたこの城を陥落させることが第一の目標だった。
明治10(1877)年2月22日明け方、城を取り囲んだ薩軍5700人が真正面と背面から一斉攻撃を始めた。城を守る熊本鎮台兵は約3500。当初から籠城策を決めて強固な陣を敷き、スナイドル銃をはじめ最新の武器を取りそろえ迎え撃った。
薩軍による一連の攻撃は激しかった。城中にいた巡査・喜多平四郎は「城を攻撃すること猛烈なり。銃丸また雨注ぐ」と例えた。政府軍側は一歩も引かず、薩軍を押し返した。
幹部の桐野利秋が「農兵、百万ありといえども一蹴」「イラサ棒(青竹)でひとたたき」と豪語するなど、薩軍側にはすぐに城を攻め落とせるとの“おごり”もあった。だが、司令長官の谷干城(土佐出身)を中心に、ぎりぎりのところで鎮台兵は踏みとどまった。熊本が落ちると薩軍が勢いづき、反乱が各地に飛び火する危険さえあったからだ。攻城戦は結局、約2カ月続き、落とせなかった薩軍にとって致命的な誤算となった。
明治10(1877)年2月22日明け方、城を取り囲んだ薩軍5700人が真正面と背面から一斉攻撃を始めた。城を守る熊本鎮台兵は約3500。当初から籠城策を決めて強固な陣を敷き、スナイドル銃をはじめ最新の武器を取りそろえ迎え撃った。
薩軍による一連の攻撃は激しかった。城中にいた巡査・喜多平四郎は「城を攻撃すること猛烈なり。銃丸また雨注ぐ」と例えた。政府軍側は一歩も引かず、薩軍を押し返した。
幹部の桐野利秋が「農兵、百万ありといえども一蹴」「イラサ棒(青竹)でひとたたき」と豪語するなど、薩軍側にはすぐに城を攻め落とせるとの“おごり”もあった。だが、司令長官の谷干城(土佐出身)を中心に、ぎりぎりのところで鎮台兵は踏みとどまった。熊本が落ちると薩軍が勢いづき、反乱が各地に飛び火する危険さえあったからだ。攻城戦は結局、約2カ月続き、落とせなかった薩軍にとって致命的な誤算となった。
□ ■ □

草牟田墓地の入口に設置されている陸軍火薬庫跡の碑=鹿児島市草牟田1丁目
「ちょっしもた」。明治10年1月下旬、政府が鹿児島・草牟田の陸軍火薬庫から鉄砲弾薬を接収。これに反発した私学校生が29日深夜、火薬庫を襲撃する事件が起きた。大隅半島・根占に狩猟で滞在していた西郷隆盛は急報に一言発し、鹿児島に戻ったという。
征韓論政変(明治6年)に破れ、鹿児島に戻った元参議の西郷。明治7年に軍事教練が中心の「私学校」、翌8年には「吉野開墾社」をつくって就業を促すなど窮乏する地元士族の救援に奔走した。
通常、県令は他県出身が政府から任命されていた。だが、鹿児島だけは地元出身の大山綱良が県令に就くなど“異例づくし”だった。秩禄(ちつろく)処分をはじめ政府の諸政策の実施は遅れに遅れ、中央からは「難治県」「独立国」と評された。
西郷らの動きに警戒を強める政府は明治10年1月初旬、中原尚雄ら各郷出身の警官らを一時帰郷させ、情報収集と同時に城下士と外城(とじょう)士の分裂工作の任務にあてた。
だが、この工作は私学校側に露見し、「ボウズ(西郷)ヲシサツセヨ」とする電報が押収されたという。逮捕された中原らは拷問され、「西郷刺殺」の密命があったとする供述が引き出された。真偽は不明だが、一連の事件で私学校生らは激高、我慢の限界を超えた。
征韓論政変(明治6年)に破れ、鹿児島に戻った元参議の西郷。明治7年に軍事教練が中心の「私学校」、翌8年には「吉野開墾社」をつくって就業を促すなど窮乏する地元士族の救援に奔走した。
通常、県令は他県出身が政府から任命されていた。だが、鹿児島だけは地元出身の大山綱良が県令に就くなど“異例づくし”だった。秩禄(ちつろく)処分をはじめ政府の諸政策の実施は遅れに遅れ、中央からは「難治県」「独立国」と評された。
西郷らの動きに警戒を強める政府は明治10年1月初旬、中原尚雄ら各郷出身の警官らを一時帰郷させ、情報収集と同時に城下士と外城(とじょう)士の分裂工作の任務にあてた。
だが、この工作は私学校側に露見し、「ボウズ(西郷)ヲシサツセヨ」とする電報が押収されたという。逮捕された中原らは拷問され、「西郷刺殺」の密命があったとする供述が引き出された。真偽は不明だが、一連の事件で私学校生らは激高、我慢の限界を超えた。
□ ■ □

2月5日、私学校に桐野や篠原国幹、村田新八ら幹部のほか、吉野開墾社や警察署の面々、旧近衛中佐の永山弥一郎らが集い、一連の事件などの対応を協議した。
永山は出兵前に、西郷が桐野と篠原を連れて上京し、政府の非を堂々と糾明すべきだと主張した。強硬論や慎重論で紛糾したが、篠原が「命が惜しいか」と一喝。桐野も「断の一字あるのみ」と発言し、方針は決まった。
最終的に、西郷の判断が仰がれた。一貫して私学校生の蜂起を抑えてきたが、無理を悟ったのか。西郷は「おいの体を皆に差しあげもんそ」と答えた。
翌朝から従軍を願い出る士族らが私学校に詰めかけ、門には「薩摩本営」と掲げられた。出立に先立ち、12日には陸軍大将・西郷らの連名で「今般政府へ尋問の筋之有り」と県庁に届け出た。しかし、尋問の具体的な内容には踏み込んではいなかった。
15日、鹿児島は50年ぶりという大雪に見舞われた。薩軍本隊は7個大隊に振り分けられ、1個大隊がおよそ2千人で構成された。意気盛んな私学校出身の兵士らは吉兆と受け止めたのか、西郷をいただき一路、北上したのだった。
永山は出兵前に、西郷が桐野と篠原を連れて上京し、政府の非を堂々と糾明すべきだと主張した。強硬論や慎重論で紛糾したが、篠原が「命が惜しいか」と一喝。桐野も「断の一字あるのみ」と発言し、方針は決まった。
最終的に、西郷の判断が仰がれた。一貫して私学校生の蜂起を抑えてきたが、無理を悟ったのか。西郷は「おいの体を皆に差しあげもんそ」と答えた。
翌朝から従軍を願い出る士族らが私学校に詰めかけ、門には「薩摩本営」と掲げられた。出立に先立ち、12日には陸軍大将・西郷らの連名で「今般政府へ尋問の筋之有り」と県庁に届け出た。しかし、尋問の具体的な内容には踏み込んではいなかった。
15日、鹿児島は50年ぶりという大雪に見舞われた。薩軍本隊は7個大隊に振り分けられ、1個大隊がおよそ2千人で構成された。意気盛んな私学校出身の兵士らは吉兆と受け止めたのか、西郷をいただき一路、北上したのだった。