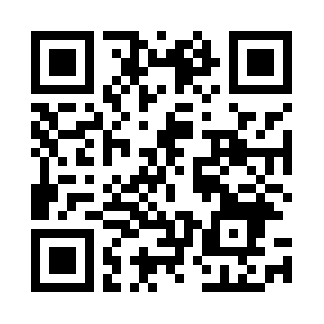第3部

プロローグ
五箇条の御誓文
慶応4(1868)年3月、京の宮中・紫宸殿(ししんでん)に衣冠束帯姿の百官が威儀を正していた。2カ月前に元服を済ませたばかりの明治天皇に代わり、神前に進み出た政府副総裁・三条実美(さねとみ)が声を発した。
「広く会議を興し、万機公論に決すべし」
この第1条に始まる「五箇条の御誓文」が明治新政府の「国是」となった。天皇親政の新たな国造りの方針を天地の神々に誓う、さながら平安時代の絵巻物のような光景だが、新しい時代の政治を示そうとの意気込みも感じられる。
第1条は会議による「公議」を掲げ、第2、第3条に「挙国一致」で取り組む姿勢を、第4、第5条には万国に対峙(たいじ)し、新たな文化を取り入れる意気込みを示した。
「広く会議を興し、万機公論に決すべし」
この第1条に始まる「五箇条の御誓文」が明治新政府の「国是」となった。天皇親政の新たな国造りの方針を天地の神々に誓う、さながら平安時代の絵巻物のような光景だが、新しい時代の政治を示そうとの意気込みも感じられる。
第1条は会議による「公議」を掲げ、第2、第3条に「挙国一致」で取り組む姿勢を、第4、第5条には万国に対峙(たいじ)し、新たな文化を取り入れる意気込みを示した。
□ ■ □
幕末、薩摩や土佐などの雄藩は「公議政体」という諸侯会議による政権を模索したが、意見の相違や主導権争いにより瓦解(がかい)した。慶応3年12月の「王政復古の大号令」は「神武創業之始(はじめ)ニ原(もとづ)キ」と初代神武天皇という原点にまでさかのぼり、日本古来の天皇の存在と近代政治の融合を試みた。
御誓文の原案「議事之体(ぎじのてい)大意」を起草したのは参与、由利公正(きみまさ)(福井藩)だった。「万機公論に決し、私に論ずるなかれ」として第5条に置いた。原文の「公論」の文字をよくよく見ると「公議」を書き直してあり、親交のあった坂本龍馬の船中八策を参考にしたとされる。
これに制度取調参与の福岡孝弟(たかちか)(土佐藩)が「列侯会議を興し」と加筆して筆頭に移したが、参与で総裁局顧問の木戸孝允(長州藩)が、「広く会議を興し」と改めた。後に、木戸のこの修正が後の民選議会設立の根拠となっていった。
公論、公議。文字は微妙に違うが今日では、いずれも世間一般の議論や意見、公平な議論を指す。だが、この時代の「公議」の意味づけは、立場や思想によって少しずつ違っていたようだ。
御誓文の原案「議事之体(ぎじのてい)大意」を起草したのは参与、由利公正(きみまさ)(福井藩)だった。「万機公論に決し、私に論ずるなかれ」として第5条に置いた。原文の「公論」の文字をよくよく見ると「公議」を書き直してあり、親交のあった坂本龍馬の船中八策を参考にしたとされる。
これに制度取調参与の福岡孝弟(たかちか)(土佐藩)が「列侯会議を興し」と加筆して筆頭に移したが、参与で総裁局顧問の木戸孝允(長州藩)が、「広く会議を興し」と改めた。後に、木戸のこの修正が後の民選議会設立の根拠となっていった。
公論、公議。文字は微妙に違うが今日では、いずれも世間一般の議論や意見、公平な議論を指す。だが、この時代の「公議」の意味づけは、立場や思想によって少しずつ違っていたようだ。
□ ■ □
明治2(69)年3月、政府は「公議所」を設け、御誓文の精神を踏まえた法整備に着手。公議人と呼ぶ各藩の代表者が集まり、租税、外交、商業、学校など多方面について検討した。これが日本で初めての議会制度だった。
諸藩の公議人は227人。大人数の議論は困難な上、根回しや事前調整にも批判が集まった。特に、森有礼(薩摩藩)をはじめ海外を知る開明派と、保守派は激しく対立した。廃刀案を提出した森が、激高した保守派に詰め寄られて命からがら逃げ出したこともあった。
保守派の一人が岩倉具視にあてた書簡には「公議輿論(よろん)を尽くすなどというのは今日の流行語」「とるに足らないことまで衆議するのはよろしくない」とある。不信感やうんざりとした様子が見て取れる。
そもそも公議所の上奏に強制力はなく、岩倉や大久保利通ら政府首脳は、その多くを採用しなかった。「衆論」による公議の上位に「至当の政治」があり、それこそが正しい「公議」政治と考えていた(明治維新史学会編「講座明治維新 維新政権の創設」)。
空転を繰り返した公議所は破綻し、同年7月には権限を大幅に縮小された「集議院」に改組された。廃藩置県後には政府への不満が集まるようになり、ついに明治6(73)年に廃止された。
諸藩の公議人は227人。大人数の議論は困難な上、根回しや事前調整にも批判が集まった。特に、森有礼(薩摩藩)をはじめ海外を知る開明派と、保守派は激しく対立した。廃刀案を提出した森が、激高した保守派に詰め寄られて命からがら逃げ出したこともあった。
保守派の一人が岩倉具視にあてた書簡には「公議輿論(よろん)を尽くすなどというのは今日の流行語」「とるに足らないことまで衆議するのはよろしくない」とある。不信感やうんざりとした様子が見て取れる。
そもそも公議所の上奏に強制力はなく、岩倉や大久保利通ら政府首脳は、その多くを採用しなかった。「衆論」による公議の上位に「至当の政治」があり、それこそが正しい「公議」政治と考えていた(明治維新史学会編「講座明治維新 維新政権の創設」)。
空転を繰り返した公議所は破綻し、同年7月には権限を大幅に縮小された「集議院」に改組された。廃藩置県後には政府への不満が集まるようになり、ついに明治6(73)年に廃止された。