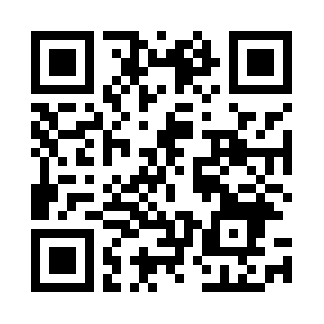第4部

プロローグ
工部省発足
旅費に困り入る次第なれば、何とぞ拝借は叶(かな)いますまいか―。
慶応元(1865)年夏のロンドン。先進的な産業技術を学ぼうと、海外渡航の禁を破って渡英した「長州ファイブ(五傑)」の一人・山尾庸三は、同じ密航者で「薩摩藩英国留学生」の学頭・町田久成に打ち明けた。旅費工面の相談だった。
山尾は日本を出発する直前に、「生(いき)たる器械」(西洋の文明技術を身につけた人間)になって帰ってくると藩上役に上申。英国着後、造船業の盛んなスコットランド・グラスゴーでの技術習得を志すが、藩からの送金もなく厳しい生活を余儀なくされ、諦めかけていた夢であった。
町田は熟考の末、他の留学生たちからカンパを募り計16ポンドを貸し与え、受け取った山尾は秋ごろグラスゴーへ旅立った。藩という枠を超え、「日本人」としての同胞意識が芽生えていた(犬塚孝明「アレキサンダー・ウィリアム・ウィリアムソン伝」)。
異国で苦学しながらも先進的な技術を身につけた山尾。5年後、その姿は日本にあった。明治3(1870)年閏(うるう)10月22日、発足したばかりの政府機関「工部省」の工部権大丞に任じられ、殖産興業政策の中核を担うこととなった。
慶応元(1865)年夏のロンドン。先進的な産業技術を学ぼうと、海外渡航の禁を破って渡英した「長州ファイブ(五傑)」の一人・山尾庸三は、同じ密航者で「薩摩藩英国留学生」の学頭・町田久成に打ち明けた。旅費工面の相談だった。
山尾は日本を出発する直前に、「生(いき)たる器械」(西洋の文明技術を身につけた人間)になって帰ってくると藩上役に上申。英国着後、造船業の盛んなスコットランド・グラスゴーでの技術習得を志すが、藩からの送金もなく厳しい生活を余儀なくされ、諦めかけていた夢であった。
町田は熟考の末、他の留学生たちからカンパを募り計16ポンドを貸し与え、受け取った山尾は秋ごろグラスゴーへ旅立った。藩という枠を超え、「日本人」としての同胞意識が芽生えていた(犬塚孝明「アレキサンダー・ウィリアム・ウィリアムソン伝」)。
異国で苦学しながらも先進的な技術を身につけた山尾。5年後、その姿は日本にあった。明治3(1870)年閏(うるう)10月22日、発足したばかりの政府機関「工部省」の工部権大丞に任じられ、殖産興業政策の中核を担うこととなった。
□ ■ □
慶応3年12月に誕生したばかりの新政府にとって、最初の難題は「宇内(うだい=世界)の大勢」を把握し、「万国と対峙(たいじ)」することだった。
列強国に肩を並べるには、国を豊かにして強兵を目指すしかなかった。“開国”したばかりの日本は、途端に貿易収支の赤字や金の流失が進んだ。政府にとって貿易不均衡を修正し、殖産興業を進めることが急務となっていた。
当初は民部大蔵省などを中心に、幕府や各藩が経営していた鉱山、機械工場を官営化するといった諸政策が進められた。しかし、政府内部での対立もあり、同省は明治3年7月に解体。数カ月後に工部省が発足した。設置目的は「百工を褒勧(ほうかん)し、智巧を開き、貨物を殖(ふや)し(中略)神州富強開化の力を逞(たくま)しく」すること。全ての職工が知恵を絞って殖産を促し、物流を増やして富国を図るとの意味。英国人技師エドモンド・モレルの提言も盛り込まれ、政治色は排除し、山尾をはじめ積極的に産業を興そうとする技術官僚らの思いが反映された。
主な業務は鉱山、鉄道、電信、灯台、製鉄など。発足当初は工部卿は置かれず、山尾が事実上のトップに就き各分野の施策をけん引した。
列強国に肩を並べるには、国を豊かにして強兵を目指すしかなかった。“開国”したばかりの日本は、途端に貿易収支の赤字や金の流失が進んだ。政府にとって貿易不均衡を修正し、殖産興業を進めることが急務となっていた。
当初は民部大蔵省などを中心に、幕府や各藩が経営していた鉱山、機械工場を官営化するといった諸政策が進められた。しかし、政府内部での対立もあり、同省は明治3年7月に解体。数カ月後に工部省が発足した。設置目的は「百工を褒勧(ほうかん)し、智巧を開き、貨物を殖(ふや)し(中略)神州富強開化の力を逞(たくま)しく」すること。全ての職工が知恵を絞って殖産を促し、物流を増やして富国を図るとの意味。英国人技師エドモンド・モレルの提言も盛り込まれ、政治色は排除し、山尾をはじめ積極的に産業を興そうとする技術官僚らの思いが反映された。
主な業務は鉱山、鉄道、電信、灯台、製鉄など。発足当初は工部卿は置かれず、山尾が事実上のトップに就き各分野の施策をけん引した。
□ ■ □
新設された各省では、とりわけ西洋諸国で見聞を広めた者が重宝された。中でも工部省に所属する渡航経験者の数は突出していた。
明治4年11月時点での同省内の洋行経験者は山尾のほか、同じ長州五傑の井上勝、薩摩藩留学生の朝倉盛明や中村博愛、佐賀出身の佐野常民らが名を連ね、4割を超えた。モレルをはじめ多数のお雇い外国人も抱え、「西洋色」の強い機関となっていた。
その一方で山尾らは同年4月に、外国人の力に頼らずとも、日本人自身の手で“自立”が維持できるよう技術者養成機関の設置を要望した。8月に「工学寮(後の工部大学校)」の創設として実現。定められた教育課程による技術習得が図られ、卒業生は行政だけでなく、民間などさまざまな舞台で活躍していった。
関西大学の柏原宏紀准教授(39)=日本経済史=は「技術官僚の思いが形となった工部省による各種施策は、明治初期の殖産興業政策の重要な部分を占め、実際の経済効果は別にして、近代化の素地(そじ)を築いたことは間違いない」と分析する。
明治4年11月時点での同省内の洋行経験者は山尾のほか、同じ長州五傑の井上勝、薩摩藩留学生の朝倉盛明や中村博愛、佐賀出身の佐野常民らが名を連ね、4割を超えた。モレルをはじめ多数のお雇い外国人も抱え、「西洋色」の強い機関となっていた。
その一方で山尾らは同年4月に、外国人の力に頼らずとも、日本人自身の手で“自立”が維持できるよう技術者養成機関の設置を要望した。8月に「工学寮(後の工部大学校)」の創設として実現。定められた教育課程による技術習得が図られ、卒業生は行政だけでなく、民間などさまざまな舞台で活躍していった。
関西大学の柏原宏紀准教授(39)=日本経済史=は「技術官僚の思いが形となった工部省による各種施策は、明治初期の殖産興業政策の重要な部分を占め、実際の経済効果は別にして、近代化の素地(そじ)を築いたことは間違いない」と分析する。