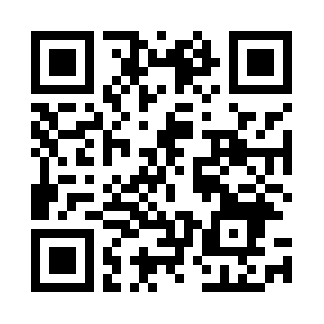第5部

プロローグ
近代西洋の文物
散切(ざんぎ)り頭を叩(たた)いてみれば、文明開化の音がする―。明治維新後、急速な西洋文化の流入が始まったが、広く口にのぼった流行(はやり)歌が象徴していた。この「文明開化」という言葉は、福沢諭吉が英語のシヴィライゼーション(文明)の訳語として使ったのが始まりだ。徳や教養のあることを意味した「文明」と進歩をはかる「開化」とを合成した造語だった。まさに日本全体の「近代化」を象徴した。
大分・中津藩出身の福沢が著した「西洋事情」初編は慶応2(1866)年に刊行、一説に25万部という今で言う“ベストセラー”になった。世界各国の歴史や政治・経済、社会、風俗までを解説する内容だ。当時、民衆に欧米に関する知識はほとんどなく、体験を基にした見聞記が反響を呼んだのは自然なことだった。
福沢は、外国にしかない文物や制度を理解し、伝えるのに苦労した。郵便制度が分かるまでに数日を費やし、銀行や保険会社の仕組みを飲み込むのにも骨を折った。原書に「バターのようにやわらかい」とあるのを「味噌(みそ)のように」と書き換えたり、難字難文を避けたりと伝わるように心を砕いた(富田正文著「考証 福澤諭吉」)。
慶應義塾福澤研究センターの西澤直子教授(57)は福沢が圧倒的に支持された理由は「分かりやすさだ」と言う。「福沢はヨーロッパで新聞の影響力を肌で感じ、情報の大切さをよく分かっていた。だから出版を手がけ、多くの人々に伝える努力を惜しまなかった」と指摘する。
維新前後の約10年間、社会や国家論を説く「学問のすすめ」「文明論之概略」を次々刊行。洋服の着方などの案内「西洋衣食住」や世界の国情を知らせる絵入りの紹介本、和暦から西洋暦への改暦を説く「改暦弁」など数々の“文明開化”の主導者として名を響かせた。
大分・中津藩出身の福沢が著した「西洋事情」初編は慶応2(1866)年に刊行、一説に25万部という今で言う“ベストセラー”になった。世界各国の歴史や政治・経済、社会、風俗までを解説する内容だ。当時、民衆に欧米に関する知識はほとんどなく、体験を基にした見聞記が反響を呼んだのは自然なことだった。
福沢は、外国にしかない文物や制度を理解し、伝えるのに苦労した。郵便制度が分かるまでに数日を費やし、銀行や保険会社の仕組みを飲み込むのにも骨を折った。原書に「バターのようにやわらかい」とあるのを「味噌(みそ)のように」と書き換えたり、難字難文を避けたりと伝わるように心を砕いた(富田正文著「考証 福澤諭吉」)。
慶應義塾福澤研究センターの西澤直子教授(57)は福沢が圧倒的に支持された理由は「分かりやすさだ」と言う。「福沢はヨーロッパで新聞の影響力を肌で感じ、情報の大切さをよく分かっていた。だから出版を手がけ、多くの人々に伝える努力を惜しまなかった」と指摘する。
維新前後の約10年間、社会や国家論を説く「学問のすすめ」「文明論之概略」を次々刊行。洋服の着方などの案内「西洋衣食住」や世界の国情を知らせる絵入りの紹介本、和暦から西洋暦への改暦を説く「改暦弁」など数々の“文明開化”の主導者として名を響かせた。
□ ■ □

神戸事件発生地の石碑。三宮神社の境内に立つ=神戸市中央区
福沢は万延元(1860)年から慶応3年にかけ、幕府の遣欧米使節に3度も参加するというまれな体験をした。
初めての渡米は27歳。軍艦奉行の従僕として、軍艦咸臨丸で勝海舟らと同行した。ホテルに敷かれた高価なじゅうたんに驚き、コルクを抜くと音がするシャンパンに肝を冷やし、そのグラスに浮く時節外れの氷にも感心した。
2度目が一番長く、約1年旅した欧州だ。香港、シンガポールなどを経てフランス、イギリス、プロシアといった列強国を訪問した。
30歳だった薩摩藩士寺島宗則も同乗していた。外国方翻訳局員の同僚で、ともに英学の才を買われ抜てきされた。二人には浅からぬ縁もあった。福沢は安政5(57)年、中津藩命で同江戸藩邸の蘭学(らんがく)塾教師に就くが、その前任者は寺島であった。日本の将来について船中で論じ合い、滞欧中は監視するような上司を「鎖国をかついで」やってきたようだと笑い合った。
福沢は購入した1冊の手帳に聞き取りなどを詳細に書き留めた。こうした体験に加え、大量に買い込んだ原書が結実したのが「西洋事情」だ。吸収した先進国の文明、文化を知らせて日本の独立を守り、新国家建設に役立てるのが使命と考えていた。
初めての渡米は27歳。軍艦奉行の従僕として、軍艦咸臨丸で勝海舟らと同行した。ホテルに敷かれた高価なじゅうたんに驚き、コルクを抜くと音がするシャンパンに肝を冷やし、そのグラスに浮く時節外れの氷にも感心した。
2度目が一番長く、約1年旅した欧州だ。香港、シンガポールなどを経てフランス、イギリス、プロシアといった列強国を訪問した。
30歳だった薩摩藩士寺島宗則も同乗していた。外国方翻訳局員の同僚で、ともに英学の才を買われ抜てきされた。二人には浅からぬ縁もあった。福沢は安政5(57)年、中津藩命で同江戸藩邸の蘭学(らんがく)塾教師に就くが、その前任者は寺島であった。日本の将来について船中で論じ合い、滞欧中は監視するような上司を「鎖国をかついで」やってきたようだと笑い合った。
福沢は購入した1冊の手帳に聞き取りなどを詳細に書き留めた。こうした体験に加え、大量に買い込んだ原書が結実したのが「西洋事情」だ。吸収した先進国の文明、文化を知らせて日本の独立を守り、新国家建設に役立てるのが使命と考えていた。
□ ■ □
維新直後、福沢は新政府からの出仕要請を固辞していた。開化政策の方向性が信用できなかったことと、「学者は国家権力から距離を置き、政策を提言すべき」との持論からだ。
明治6(73)年設立の学術団体「明六社」の機関誌では「学者は在野にあるべき」との福沢の主張を巡り論争になった。発起人で薩摩藩出身の森有礼は、国家への義務を果たしうる自立的学者の必要性を説き、福沢に反論した。
福沢は、主張通り官職に就かなかった。明治元年、「慶應義塾」と命名した東京の芝新銭座(現浜松町)の学塾を拠点として教育者、言論人、出版事業者として歩んだ。
「列強と対等の国づくり」という志を同じくしながらも、外交や教育畑など政府の要職を歴任した森や寺島とは対照的だ。西澤教授は「精神的、経済的に独立した人材が、西欧諸国と並ぶ国家形成につながると考えていた。人づくりが最優先だった福沢にとって自然な選択だった」とみる。
明治6(73)年設立の学術団体「明六社」の機関誌では「学者は在野にあるべき」との福沢の主張を巡り論争になった。発起人で薩摩藩出身の森有礼は、国家への義務を果たしうる自立的学者の必要性を説き、福沢に反論した。
福沢は、主張通り官職に就かなかった。明治元年、「慶應義塾」と命名した東京の芝新銭座(現浜松町)の学塾を拠点として教育者、言論人、出版事業者として歩んだ。
「列強と対等の国づくり」という志を同じくしながらも、外交や教育畑など政府の要職を歴任した森や寺島とは対照的だ。西澤教授は「精神的、経済的に独立した人材が、西欧諸国と並ぶ国家形成につながると考えていた。人づくりが最優先だった福沢にとって自然な選択だった」とみる。