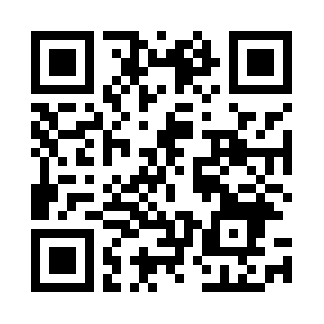第8部

プロローグ
地租改正
「租税収納の法制、都鄙(とふ)市村とも公平適当を得候(そうろう)様改正仕(つかまつり)たく」。明治4(1871)年10月、厳しい財政事情に頭を悩ます大蔵卿の大久保利通は、幕藩体制から続く年貢制度を抜本的に変える税制改革を模索していた。重視したのは「公平性」だった。
江戸時代、主たる税は領主(藩や幕府)に納める年貢(米納)であり、原則農民にだけ課せられていた。税率は収穫高で決まるが、各藩によって異なった。支払い義務のない士族や商人は農民より割合が少ないとはいえ、世の中に不公平感がくすぶった。
年貢は藩の取り分で、明治政府は当初、旧幕府から引き継いだ天領などからの税収しかなかったため、財政はぜい弱だった。同年7月に実施した「廃藩置県」は財源確保も視野にあり、早急な税制改革が目指された。
政府にとって重要なことは、各藩が得ていた同等の税収を一元化して確保、近代国家として国民に公平な税負担を求めることだった。資本主義化に対応するため、従来の米納を見直し、金納制を導入する、明治6年の「地租改正」につながった。
江戸時代、主たる税は領主(藩や幕府)に納める年貢(米納)であり、原則農民にだけ課せられていた。税率は収穫高で決まるが、各藩によって異なった。支払い義務のない士族や商人は農民より割合が少ないとはいえ、世の中に不公平感がくすぶった。
年貢は藩の取り分で、明治政府は当初、旧幕府から引き継いだ天領などからの税収しかなかったため、財政はぜい弱だった。同年7月に実施した「廃藩置県」は財源確保も視野にあり、早急な税制改革が目指された。
政府にとって重要なことは、各藩が得ていた同等の税収を一元化して確保、近代国家として国民に公平な税負担を求めることだった。資本主義化に対応するため、従来の米納を見直し、金納制を導入する、明治6年の「地租改正」につながった。
□ ■ □
地租改正の構想を立案したのは神田孝平(旧幕臣)や陸奥宗光(後の外務大臣)であったが、その実務を任されたのは薩摩藩出身の大蔵省租税権頭、松方正義であった。廃藩置県の断行と全国一律の租税実現を訴えていた松方を、同郷の大久保が“抜てき”したのだった。
松方は小松帯刀、五代友厚と同じく天保6(35)年生まれ。早くから活躍した五代とは友情を結び、維新後に財政通として大久保の信頼も得るようになった。
初代の日田県知事(慶応4~明治3年)に就き、地方の実態を目の当たりにしていた松方は、「民租は政体最大の根源にて容易に動かし難(がた)い事件に御座有(ござあ)るべし。併(しか)し乍(なが)ら仁政は経界を正すより始(はじめ)とこそ承(うけたまわる)」と意見書を提出。税制は政治の根幹で、良い政治は経済・財政を正すことが肝要とし、改租の必要性を訴えて並々ならぬ決意で取り組んだ。
改革の一番は、従来の収穫高に応じた米納から、それぞれの土地の価値(地価)を定め、地価の3パーセントを地租としてお金で納める金納方式への変更だ。旧来通りでは米価変動で税収が大きく変わるが、金納にすることで収入安定化を図ることができた。
さらに政府は、藩政時代に禁止されていた「田畑勝手作りの許可」(明治4年)や、「田畑永代売買の解禁」(同5年)を実施。農民に土地の自由な利活用を認めた上で、土地所有を公認して地租負担者に位置付けた。
江戸時代、土地の所有権は幕府(藩)に帰属していたが、政府は私有財産権を保障した。すなわち、近代国家の原則である国民の「権利」を認めつつ、納税の「義務」を課したのだった。土地売買はそれまでも暗黙の了解で行われていたが、税制だけでなく土地制度の点でも転機となった。
松方は小松帯刀、五代友厚と同じく天保6(35)年生まれ。早くから活躍した五代とは友情を結び、維新後に財政通として大久保の信頼も得るようになった。
初代の日田県知事(慶応4~明治3年)に就き、地方の実態を目の当たりにしていた松方は、「民租は政体最大の根源にて容易に動かし難(がた)い事件に御座有(ござあ)るべし。併(しか)し乍(なが)ら仁政は経界を正すより始(はじめ)とこそ承(うけたまわる)」と意見書を提出。税制は政治の根幹で、良い政治は経済・財政を正すことが肝要とし、改租の必要性を訴えて並々ならぬ決意で取り組んだ。
改革の一番は、従来の収穫高に応じた米納から、それぞれの土地の価値(地価)を定め、地価の3パーセントを地租としてお金で納める金納方式への変更だ。旧来通りでは米価変動で税収が大きく変わるが、金納にすることで収入安定化を図ることができた。
さらに政府は、藩政時代に禁止されていた「田畑勝手作りの許可」(明治4年)や、「田畑永代売買の解禁」(同5年)を実施。農民に土地の自由な利活用を認めた上で、土地所有を公認して地租負担者に位置付けた。
江戸時代、土地の所有権は幕府(藩)に帰属していたが、政府は私有財産権を保障した。すなわち、近代国家の原則である国民の「権利」を認めつつ、納税の「義務」を課したのだった。土地売買はそれまでも暗黙の了解で行われていたが、税制だけでなく土地制度の点でも転機となった。
□ ■ □
「公平画一」を原則に、全国一律の基準で実施された地租改正。農民における負担割合(地価3パーセントの場合)は全国を平均すると、藩政時代とほぼ変わらない結果だが、地域別でその度合いは違った。
藩政時代は各藩によって税率が異なるものの、田地に比べて畑地の税負担は低く抑えられていた。しかし、地租改正では田地の地価が低く抑えられた一方、畑地は高く見積もられることとなった。
畑作中心農家にとっては増税となり、畑地の割合が高い関東や鹿児島では負担増が顕著となった。当然、田地の割合が高かった山陰や近畿では減税となった。
地租改正は地価を新たに設定するため、長く実施されてこなかった「検地」をはじめ、諸作業に8年ほどの歳月を費やして完了した。改租直後における国税収入の7~8割を地租が占め、財政の安定化に大きく貢献する結果を生んだ。茨城大学名誉教授の佐々木寛司さん(69)は「近代国家の形成を目指した明治政府の諸政策の前提には、地租改正の成功があったといっても過言ではない」と指摘した。
藩政時代は各藩によって税率が異なるものの、田地に比べて畑地の税負担は低く抑えられていた。しかし、地租改正では田地の地価が低く抑えられた一方、畑地は高く見積もられることとなった。
畑作中心農家にとっては増税となり、畑地の割合が高い関東や鹿児島では負担増が顕著となった。当然、田地の割合が高かった山陰や近畿では減税となった。
地租改正は地価を新たに設定するため、長く実施されてこなかった「検地」をはじめ、諸作業に8年ほどの歳月を費やして完了した。改租直後における国税収入の7~8割を地租が占め、財政の安定化に大きく貢献する結果を生んだ。茨城大学名誉教授の佐々木寛司さん(69)は「近代国家の形成を目指した明治政府の諸政策の前提には、地租改正の成功があったといっても過言ではない」と指摘した。