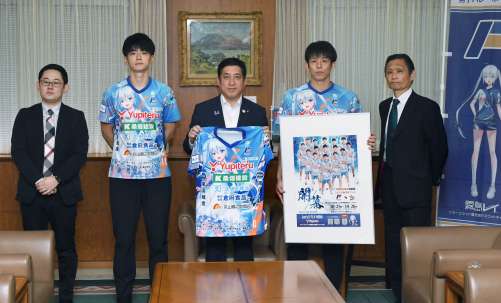「楽してる」と誤解されがちな不登校…違う学び方、学びやはある 養護教諭ら、学校だけじゃない連携の大切さ訴え
2023/08/09 18:00

県内の2021年度の不登校生数は3688人で、4年連続最多となっていることからテーマに設定。7月28、29日に鹿児島市の鹿児島大学付属中学校であり、約120人が参加した。
出水中学校の指宿将麻教諭(33)は、教室以外の居場所「心の教室」を紹介。相談員の常駐や生徒の実態に応じた教員の出前授業、無人の空き教室など学習できる部屋を複数用意する取り組みのほか、校外の居場所として、自習ができる市の自立支援施設「ほっとハウス」との連携も説明。「不登校を問題視しすぎるのも良くない。子どもを第一に考えたい」と話した。
三篠小(広島市)の阿部京子教諭(50)は、ほぼ全ての広島市立小中学校に設置する「ふれあいひろば」を挙げた。不登校傾向の子どもたちが時間割を決め、工作などの体験活動も可能。他の児童や保護者から「楽をしている」と見られがちなため、「勉強方法や場所が違うこともあると繰り返し伝える必要がある」と強調した。
参加した三船小(姶良市)の塩入智子教諭(52)は「学校だけで解決しようとせず、福祉や行政とつながりながらみんなで子どもを育てたい」。川畑まゆみ顧問(62)は「不登校対応は一部の教員任せになりがち。子どもの心や体調の変化に気づく機会が多い養護教諭や担任を核としつつ、学校全体で情報共有し向き合ってほしい」と話した。