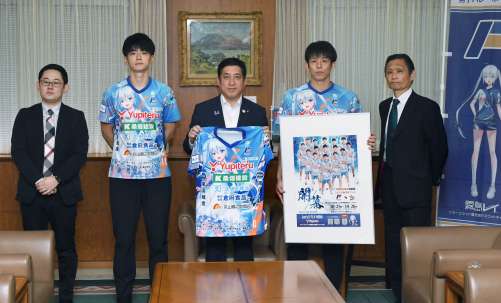避難のため海上自衛隊の船に乗り込む住民役の学生ら=16日午前10時36分、鹿児島市桜島赤水町の赤水港
「大規模噴火、全島脱出だ」…能登半島地震を教訓、孤立集落から海上救出 住民ら1700人、桜島で総合防災訓練
2024/11/16 20:54
訓練は今年で55回目。山体膨張や群発地震が観測され大規模噴火が切迫したとして、気象庁が噴火警戒レベルを現状の3(入山規制)から4(高齢者等避難)、5(避難)へと引き上げ、全島民が島外へ避難する想定で実施した。
午前10時半に全島避難指示が出ると、住民は自宅に「避難完了板」を掲示してバスやマイカーで桜島港と黒神口付近へ移動。観光客が利用する施設では、外国人客を想定して3カ国語で放送し、指さし確認カードを使って避難を支援した。
能登半島地震では道路が寸断され、孤立地域が発生したことから、複合災害の発生も想定した。237人が住む赤水地区ではマグニチュード5の地震に伴い、土砂崩れと橋の損壊で陸路の避難ができなくなったとして、海上保安庁の巡視艇と海上自衛隊の船が救助に向かった。消防職員や陸上自衛隊員が住民役の専門学校生を退避舎から赤水港へ誘導し、巡視艇や海自の船に乗って島外に脱出した。
毎年訓練に参加している同市桜島藤野町の橋口修身さん(84)は「各地で災害が起きているが、桜島の噴火は予期できず、絶えず気配りしないといけない」と気を引き締めた。子ども2人を連れて参加した桜島野尻町の主婦磯辺郁美さん(43)は「訓練に参加することで不安を少しでも減らしたい。実際には避難の準備が大変だと思う」と話した。