クラスメソッドの“AIDD Boost Team”が挑む!「AI駆動開発」の現在地と未来
クラスメソッドは、「AI駆動開発支援サービス」や「AI支援型テスト駆動開発フレームワーク「Tsumiki」の提供など、いち早くAIを導入したソフトウェア開発のあり方を見つけるべく、日々探究しています。今年から部門を横断したメンバーで構成された「AIDD Boost Team」も発足し、社内のAIに関する知識差を埋め、早期に実践で活かせるよう取り組んできました。
今回は、クラスメソッドが考えるAI駆動開発の定義や現在地、そして未来について「AIDD Boost Team」に語ってもらいました。

AI駆動開発の定義は会社ごとに異なるフェーズ
— まずは、クラスメソッドが「AI駆動開発」をどのように定義しているのか教えてください。
大橋:我々は、ただコードをAIで自動生成するプロセスを「AI駆動開発」と呼んでいるわけではありません。要件定義、設計、実装、テスト、運用などの、ソフトウェア開発の全工程に生成AIを積極的に組み込むことを指しています。今はまだ、クラスメソッドも含めて「コード生成の効率化」に対してAIを用いている会社が多いと思います。しかし、近い将来、AIがあることを前提に、「AIで効率化」の段階から、「AI起点で」ワークフロー自体を再設計していくような流れになっていくと思います。
どこまでがAI駆動開発かという明確な線引きは、まだ業界全体でも模索中だと思います。実際に取り組み、試行錯誤の結果を発信し、具体的に提供できるサービスに昇華する意義があると考えています。
— AIDD Boost Teamが発足された背景について教えてください。
大橋:クラスメソッドには、開発やインフラ構築を担う部門が7つあります。組織規模が大きいので、正直なところ、AIツールの活用度合いには、部門ごとの差が生じています。エンジニア主導でどんどん活用が進んでいく一方、なかなか試せずにいるメンバーもいます。結果として、ノウハウの偏りにつながってしまいます。そこでAIに対して全社的に取り組む必要があると考え、AIの活用度合いが高いメンバーに声をかけ、「AIDD Boost Team」を今年の6月に立ち上げました。
現在は各部門から2〜3人ずつが参加し、約20人で活動を推進しています。しかし、20人規模となると日々の活動の小回りが効きづらいため、中でも特に積極的にAIを活用している5人が中核となってチーム運営をしています。
菊池:エンジニアの中には、ツールを触るのが好きで、どんどん試す人と、ちょっとハードルを感じている人がいて。そういう人たちにも使えるように、社内の情報を整備したり、失敗談を共有したりするのがBoost Teamの役割だと思ってます。
大橋:流行りの波が激しいのがAIツールです。「数カ月前まで主流だったツールが、今では使われなくなっていることも少なくありません。だからこそ「誰かがキャッチアップして、情報を貯めて、みんなに伝える」っていう仕組みが必要なんです。

活用状況の可視化から、勉強会、社外支援まで多層的に展開
— AIDD Boost Teamの具体的な活動を教えてください。
佐藤:例えば、ツールの利用状況を定期的にアンケートで集めて、どのツールがどの程度業務に使われているかを数値で把握しています。そのデータをもとに、利用レベルの偏りを可視化して、改善へのアクションに繋げています。
筧:AWSが実施している3日間のハンズオンワークショップにも、メンバーの積極的な参加を促しています。現在はまだ、我々自身が受講者として学んでいますが、将来的にはクラスメソッドとしてお客様向けにもワークショップや講座を提供していく予定です。
高橋:AWSが提供する生成AI「Amazon Bedrock」とAI コーディングエージェントである「Cline」を組み合わせて使う、「Cline with Amazon Bedrock」というハンズオンイベントも実施しました。これは社外の方に向けて、しかも非エンジニアの方にも来ていただくイベントだったのですが、参加された皆さんは、とにかくAIでできることの幅広さに驚かれていましたね。AI駆動開発はエンジニアだけのものではないと考えていましたが、プロダクトマネージャーのような方が短時間でモックを作成しエンジニアと連携しやすくなるシーンが、具体的に想像できました。
クローズドに社内で行ったハンズオンでは、用意していた課題と全然違うゲームを作り始める人もいるほどでした(笑)。AI駆動開発に対してワクワクしてくれた証拠だと思います。
菊池:私は月1回の社内勉強会を担当しています。登壇者は毎回3〜4人集まってくれていて、ClaudeやCursor、Notion AIなどの具体的なTipsや、社内だからこそ話せる「うまくいかなかったこと」も含めて、赤裸々に共有してもらっています。アンケートでも満足度は毎回ほぼ100%。やっぱり「現場のリアル」は学びになっているようです。
情報が流れやすい時代だからこそ、社内に“ナレッジの定点”を
— Claude Codeのナレッジレポジトリなども公開されているそうですね?
筧:初めは社内向けに整備していたClaude Codeの活用ノウハウを、「CCナレッジ(https://ccknowledge.com/)」というサイトにまとめて社内向けに公開しています。生成AIの情報はアップデートが早すぎて「これ、どこで見たっけ?」となることも多いです。しっかりとストックして情報を残せる場所が必要だと思い、始めました。
佐藤:この領域で世の中に発信されている情報は、玉石混交です。技術的な裏付けが薄い情報が拡散されていたり、表面的なTIPSだけが独り歩きしていることも多々あります。だからこそ、クラスメソッドが手を動かし、検証して「これは使える」「これは気をつけた方がいい」といった実践知を発信していく必要があると思っています。
— 中でも反響の大きかった取り組みがあれば教えてください。
佐藤:高橋さんのブログ(https://dev.classmethod.jp/articles/shuntaka-mcp-study/)は社内外でかなり反響がありました。MCPの基礎に関する社内勉強会資料を公開しています。
菊池:NotebookLMを使って、社内勉強会の記録をAIで整理してブログにした記事(https://dev.classmethod.jp/articles/study-session-sharing-with-notebooklm-google-workspace/)にも反響があありました。せっかく実施する社内勉強会なので、知見が少しでも広がるようにと、録画と文字起こしを元に見返しやすい形に情報を編集する取り組みです。
— 社外向けのサービス展開について教えてください。
佐藤:今年4月から「AI駆動開発支援サービス(https://classmethod.jp/services/aidd/)」という形で、社内で培ったノウハウをお客様にも提供し始めました。生成AIを業務にどう組み込むかに悩んでいる企業が多い中で、すでに30件以上の問い合わせをいただいています。非常に関心が高い分野なんだと感じています。
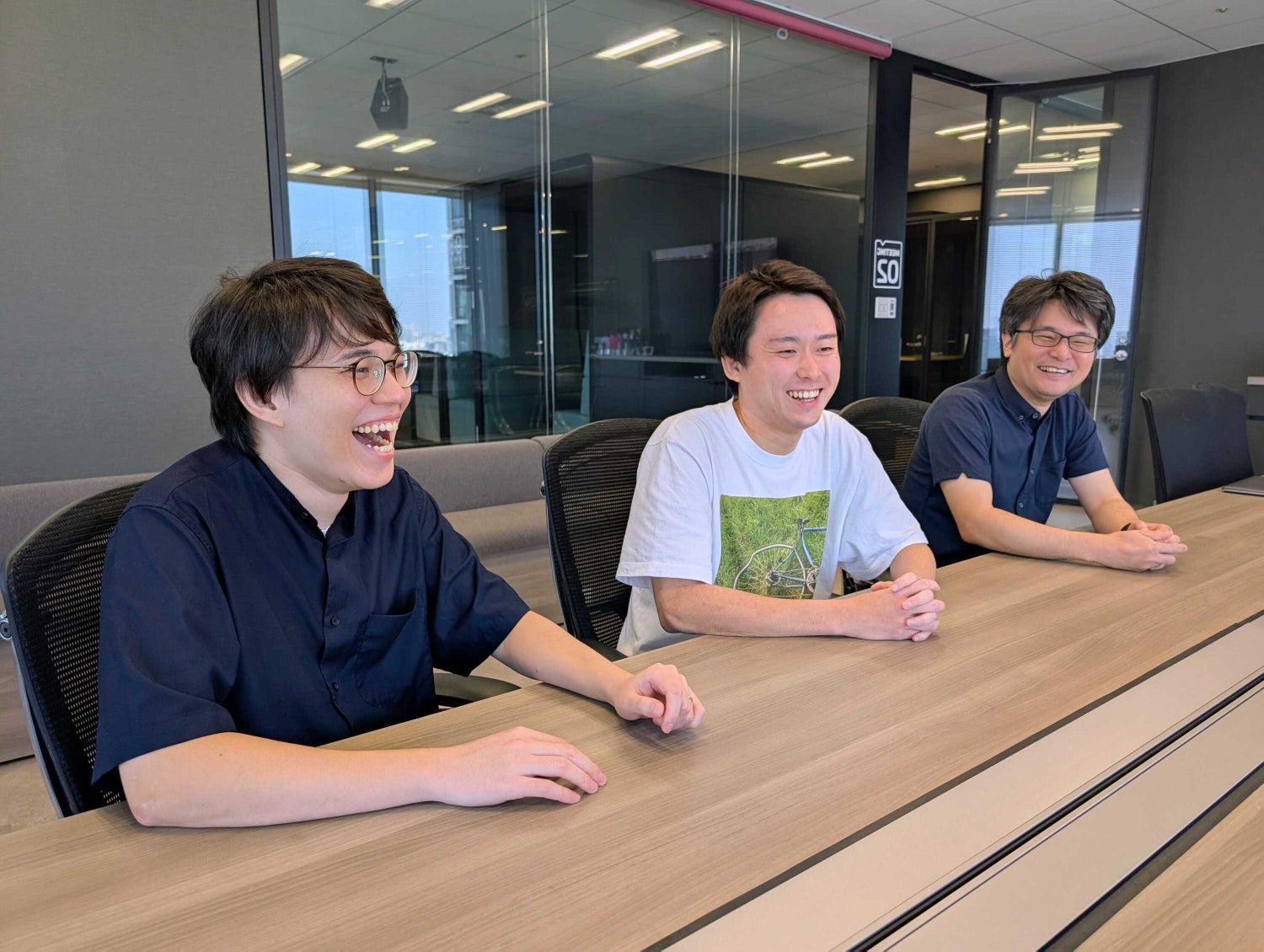
AIツール導入のスピードを支える社内文化
— このようなAIを高速で試す会社風土を作るためには、情報システム部門をはじめ、組織基盤は重要だと思います。
大橋:クラスメソッドの良いところは、トップダウンとボトムアップのバランスがいいところなんです。代表の横田は、週末になると朝までAIを試すほど熱心で、社員よりも早く「やってみた」情報をSlackに投稿することがあるほどです。代表が自ら、あれだけ楽しそうにAIを試していると、他の社員も自然と試してみたい気持ちが醸成されるんです。
菊池:ツールの導入も早いです。社員が「このAIツールを使いたい」と伝えたら、情シスが並走して検証して、すぐに環境が整備されるのがクラスメソッドの良いところです。他社では導入に数ヶ月かかったという話を聞くこともありますが、クラスメソッドにおいてはそのようなことは起きたことがないです。このスピード感は恵まれた環境の一因だと思います。
高橋:情シス部門は、こちらが伝える前にすでに動いてくれていることも多く、驚いてしまうほどです。セキュリティチェックも並行して進めてくれるため、現場としては非常に助かっており、どこよりも早く、多様なAIツールを業務で試せていると実感しています。
今は「未来の標準」を探るフェーズ
— 最後に、クラスメソッドとしてのAI駆動開発における今後の展望について教えてください。
大橋:技術の進化が速すぎる時代です。だからこそ、今の時点で何かを「標準」として固定してしまうのは、正直危険だと考えています。今はとにかく、多様なツールに触れてみて、「これは業務で使える」「このツールはまだ発展途上だ」といった、試行錯誤してAIの技術発展に触れ続ける時期だと捉えています。だからこそ僕ら AIDD Boost Team が率先して試し、ナレッジを溜め、社内外に展開していく意味があると思います。
佐藤:個人的には、「正しい情報を実践から見極めて発信する」ことがこのチームの存在意義だと思ってます。まだまだ情報の信頼性にばらつきがある生成AI領域だからこそ、地に足のついたクラスメソッドらしい取り組みを続けていきたいです。
筧:クラスメソッドは先日、Anthropic社との連携を発表しました。最先端の情報に触れながら、現場でどんどん試していける環境があるのは、エンジニアにとってすごく魅力的だと思います。今後も、生成AIベンダーと連携を強め、最新の知見を社内外に発信していきたいです。
— ありがとうございました。
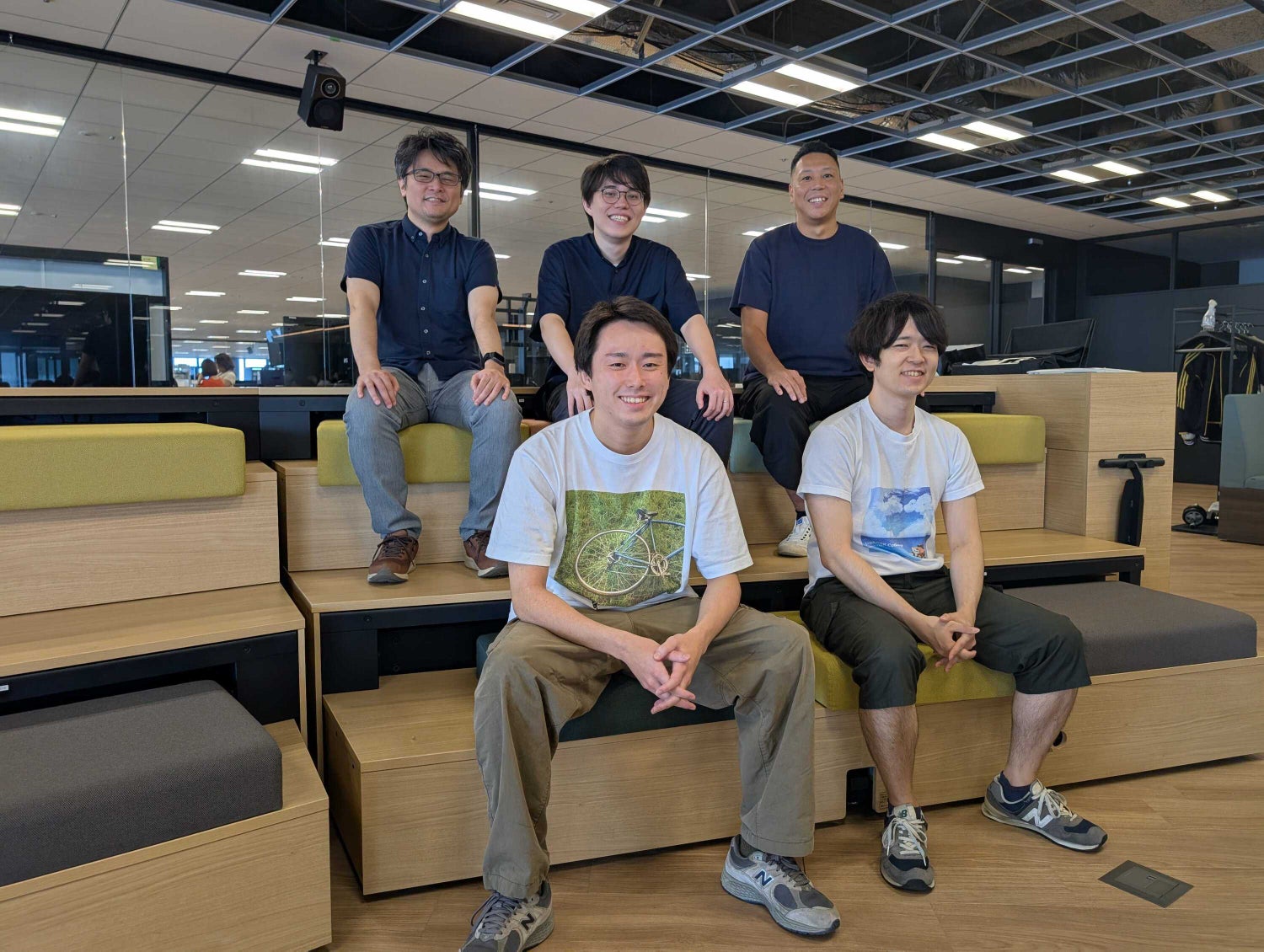
登場人物プロフィール

大橋力丈 / 取締役 兼 製造ビジネス・テクノロジー部 部門長
金融系システム開発を経験したサーバーサイドエンジニアとして、2009年9月にクラスメソッドに入社。入社後はモバイルアプリやサーバーレス関連のアプリケーション部門で責任者を務め、現在は製造業のお客様向け事業に従事している。また、社内ではAIDD-BoostTeamとしてAI駆動開発の普及活動を推進しており、「AI駆動開発コンソーシアム」の発起人兼副幹事も務めている。

佐藤智樹 / 製造ビジネステクノロジー部 エンジニア兼マネージャー
電力小売事業の基幹システムの運用やテストに従事。開発でLambdaやIaCを実務で活用したく2020年2月に入社。IoT関連のサービスに従事後、現在はAI駆動開発で使われるサービスや効率化手法の研究調査を実施。JAWS-UG CDK支部も傍らで運営。Japan AWS Top Engineersに選出(2023-2025)。AWS Community Builder Dev Tools部門選出 (2022-2025)。
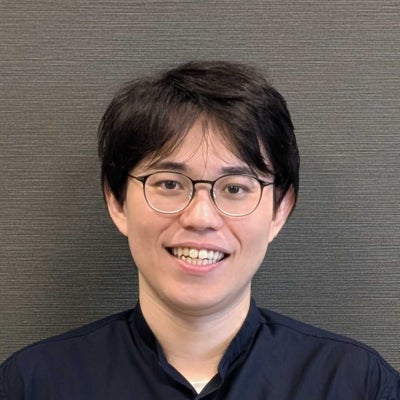
高橋俊一 / 製造ビジネステクノロジー部 サーバーサイドエンジニア
金融系の事業会社で開発業務を経て、2019年にクラスメソッドに入社。IoTやWebアプリのサーバーサイド開発を行う。現在は加えて生成AI関連ツールの検証やAIエージェント開発に従事。shuntakaで情報発信をしている。

菊池聡規 / クラウド事業本部 コンサルティング部 マネージャー
自社Webサービスをもつ企業を経て、クラスメソッドにジョイン。コンテナとTerraformが好きで、現在はAWSに関するコンサルティング業務を中心に活動。ずっとインフラ畑でやってきた人。Japan AWS Top Engineersに選出(2024-2025)。
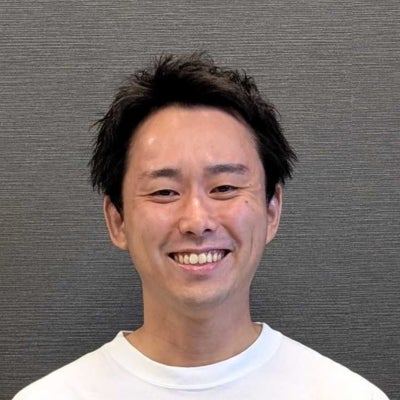
筧剛彰 / AI事業本部 生成AIインテグレーション部 ソリューションチーム
2019年10月、クラスメソッド入社。生成AIを中心に、企画・開発から導入コンサル、伴走支援までを担当するソフトウェアエンジニア。自社プロダクト「AI-Starter」のサービスオーナー。著書に「ビジネスのためのChatGPT活用ガイド」。Japan AWS Ambassadors 2025を受賞。Japan AWS Top Engineers に選出(2021-2023)。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ




















