J-SPARC祭り2025 レポート
8月28日、日本橋で開催された「J-SPARC祭り2025」。7年で育った52の共創プロジェクトと14件の事業化、官民共創活動の舞台裏が、具体例とともに語られた。各国で宇宙産業への取組が進む中、人材育成、民間事業化のスピード感含めて、どう取り組むべきか。登壇者たちの本音から、宇宙を日本の成長へと変える未来に向けた挑戦課題が見えてきた。

第1章 開会のことば
総合MC:榎本 麗美 様(宇宙キャスター/J‑SPARCナビゲーター)
皆さま、本日は「J-SPARC祭り2025」にご来場くださいまして、誠にありがとうございます。会場には、すでにJAXAの宇宙イノベーション・パートナーシップ「J-SPARC」をご存じの方が多くお集まりいただいているかと思いますが、改めて本取り組みについてご説明いたします。J-SPARCは、宇宙産業を日本経済の成長産業とすることを目指し、企業や大学などとJAXAが共創するオープンイノベーション型の研究開発プログラムです。2018年の立ち上げから7年が経過し、本日の「祭り」は、これまでの成果と現在の活動、そして今後の計画を広く共有し、より多くの皆さまに参画していただくために企画されました。私自身、2021年からJ-SPARCナビゲーターを務めており、年々高まる宇宙ビジネスの熱気に感慨深さを感じております。本日は、この盛り上がりを会場の皆さまと分かち合い、次への気持ちをさらに高める一日にしたいと考えております。

来賓挨拶:梅原 弘史 様(文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課長)
近年の日本の宇宙分野の変化を振り返り、2000年代後半以降の法整備(宇宙基本法・宇宙活動法)や国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」の活用等を通じて、我が国の宇宙活動の裾野が広がってきたことを確認しました。さらに、民間の主体的な取り組みが、今まさに力強く動いている現状を強調されました。
我が国は人口減少局面にありますが、宇宙に目を輝かせる子どもや若い世代がこの分野に飛び込んでくるなら、日本の未来はまだまだ明るいはずです。その時代が到来するまでの間、現役世代が盛り上がりをつなぎ、官民共創や民間主体の事業化の流れをいっそう確かなものにしていかねばならない――梅原課長は、こうした決意を述べられました。
政策面では、政府の宇宙基本計画のもと、文部科学省は研究開発にとどまらず産業競争力の強化にも取り組んでいること、また、JAXAによるJ-SPARCの推進を大きな柱の一つとして支援していることが示されました。また、宇宙輸送分野の研究開発プログラムの推進、SBIRフェーズ3基金による民間ロケットやスペースデブリ低減への支援、さらに関係府省連携で創設された宇宙戦略基金を通じ、企業・大学の挑戦的な取組へ積極的に支援していく方針が共有されました。
また、人材育成は文部科学省の最重要課題の一つであり、小中高・高専・大学までの様々な教育機会を通じて、宇宙分野に関心を持つ子どもたちの芽を育み、将来へと連続的につないでいく取り組みの必要性を強調されました。最後に、本イベントに集う皆さまが、まさに日本の宇宙分野と官民共創を支える中心的プレイヤーであるとの期待が述べられ、関係府省、JAXA、企業や大学などの垣根を越え、大きなビジョンのもとで目線をそろえて、共に歩もう、という呼びかけで締めくくられました。
以上をもって、J-SPARC祭り2025の幕が上がりました。本稿では、続く章でJ-SPARCの軌跡と現在地、そしてこれからの挑戦を丁寧に追ってまいります。

第2章 J-SPARCの軌跡とさらなる挑戦
登壇:高田 真一(JAXA 新事業促進部 事業開発グループ長)
J-SPARCは官民間の技術循環型モデル
・JAXAの技術シーズを、民間のニーズや課題を取り込む形で研究開発・高度化を進め、
・その成果をJAXAプロジェクトと民間ビジネスの双方で活用し、
・実証・実運用からのフィードバックを、JAXAの次代の研究開発へつなげる
――というサイクルを徹底しています。
この循環を機能させるため、民間側の強い事業化コミットメントと、それに応えるJAXA研究開発活動のスピード感・出口志向を重視していることが強調されました。
7年間の主要事業実績
- 事業アイデア:約300件超の応募から、共創プロジェクト52件を開始。
- 事業化:52件中、14件がすでに収益を伴う出口に到達。
- 継続率:卒業後の独自継続16件、J-SPARC内で継続中16件を含め、全体の約88%が活動継続。
- 参画企業:52件の共創活動を通じ、累計約200社が連携。そのうち約75%は非宇宙系企業。
- 分野の広がり:小型ロケット、小型衛星コンステ、データ利用、エンタメ等、8つの事業領域と8つの異業種連携を展開。
- 投資・収益:民間投資は累計40億円超、JAXAの研究開発投資は約10億円。レバレッジの効いた連携。また、企業等の売上累計は40億円に到達。
- 資金調達:共創企業(主にスタートアップ)による外部資金の獲得額は、累計で約2,300億円規模に到達。
技術面への波及
共創活動を通じて、JAXAの研究開発の加速・効率化した事例が多数生まれています。JAXAの技術が民間の衛星やロケットに実装されることで、JAXA単独では機会が限られる実証が前倒しで進むなど、技術循環の好事例が積み上がっています。
プロデューサー体制
J-SPARCでは「プロデューサー」と呼ばれる専門職が、各事業に伴走し、企業とJAXAの向きを丁寧に合わせて双方の力を最大化させる役割を担っています。1件ごとの民間事業者とJAXAとのチームを丁寧にデザインすることが、成果の継続・拡張につながっていると考えています。
政策との接続・広がる影響
J-SPARC共創活動は、政府文書・計画にも反映され、宇宙輸送や衛星利用、低軌道(ISS)活用などでJ-SPARCの活用が言及されるようになりました。ここまで、年間平均ではおよそ20件の共創活動を展開しており、J-SPARC内での事業化に加えて、SBIRや各種基金へと橋渡しされる事例も増えつつあります。
メッセージ:2030年代の時代をつくるために、“今”のスタート
宇宙ビジネスは新たな局面に入っており、2030年代から振り返ったときに「2020年代に切ったスタートが時代をつくった」と言えるよう、いま確かな一歩を踏み出すべきだと呼びかけました。そのためにも、J-SPARCを起点に新しい事業アイデアやコンセプトを生み出し、政府の新プログラムへ確実に橋渡ししていく体制を強化していきます。
今後の重点:基盤整備と実装の加速
- 新規事業の創出:共創・事業化の推進を継続しつつ、より早期から出口設計を行います(従来からの取組の継続・発展)。
- 新しい事業アイデアの発掘:何よりタマゴメが大事。
- 橋渡し機能の強化:宇宙戦略基金含む新たな施策への接続につなげるための“前段の設計”。
- 基盤整備:宇宙ならではの難易度(打上げ、環境、他)に対応するため、ツールや試験設備などの基盤を先行的に整備し、産業全体の実装スピードを底上げ。
最後に、会場ではJ-SPARCの団扇(うちわ)と事例ハンドブックを配布し、オンラインからもダウンロード可能であることが案内されました。これまでの取り組みを俯瞰できる資料として活用してほしい、とのメッセージで本章の説明は締めくくられました。

第3章 今の宇宙産業の課題と今後への期待(対談)
登壇者
- 経済産業省 製造産業局 宇宙産業課 宇宙産業課長・高濱 航 様
- 宇宙エバンジェリスト/一般社団法人Space Port Japan 創業理事・青木 英剛 様
本章では、お二人のトークセッションとして、現在の宇宙産業を取り巻く環境、官民連携の要点、そしてJ-SPARCへの期待について議論された内容を要約いたします。
1. 世界と日本のいま
- グローバル市場の拡大:宇宙産業の世界市場は2005年の約20兆円規模から、2024年には約90兆円(約6,000億米ドル)規模へと拡大しています。今後も放送・通信、測位・位置情報、衛星データ利活用を中心に拡大が見込まれます。
- 日本の存在感と期待:海外からはJAXAの確かな実績と日本のものづくり力への信頼が厚く、UAEをはじめアジア・欧州からの連携要請が高まっています。日本語中心の情報流通という壁はある一方、部材・加工から電子部品に至る製造力と、円安に起因する相対的コスト競争力が外貨獲得の追い風になりうるとの指摘がありました。
- 政府予算の拡充:日本の政府宇宙予算はこの10年で約2.5倍に拡大し、直近では約1兆円規模となりました。国際的にも上位水準であり、民間側の挑戦を後押しする基盤になっています。
2. 日本の課題とポテンシャル
- 輸出入の偏り:日本の宇宙市場に占める輸出は約3%で、依然として国内完結度が高い構造です。衛星部品等の輸出は進みつつあり、データ利活用やソリューションの海外展開が今後の鍵になります。
- 「三すくみ」から 高循環 へ:ロケット・衛星・宇宙利用が相互依存し合って全体の足かせになる「三すくみ」の産業構造を、伸びる部分が全体を牽引する好循環へ転換する必要があります。
3. 官民連携の要所
- 二階建て戦略:①政府連携(公共調達・国家インフラ)と②民需(グローバル外需・商用市場)の両輪で事業を組み立て、資金と実績のスピンを加速させます。米国では政府契約と民間投資の相互作用が新興企業の成長を押し上げました。
- 役割分担とシナジー:
- 開発分野(ロケット/衛星/月面着陸等):官民それぞれの強みを持ち寄り、競争と補完を両立します。
- 初期投資が重い基盤(試験設備・宇宙港等):官がベースを整備し、民が機動力で活用・高度化する形が有効です。
- 市場形成とルールメイキング(デブリ低減・STM等):R&Dと国際ルール整備を官民共同戦で 同時並行的に進めることが不可欠です。
- 大企業×スタートアップ:日本では大企業が出資・技術連携でスタートアップを支える事例が増加しており、国家プロジェクトの下支えとしても機能しています。
4. J-SPARCへの期待
- 利用産業の本格参画:非宇宙産業のプレイヤーが多数参画し、利用側の視点から「どの宇宙技術が価値か」を明確化する場としての進化が期待されます。
- スピードのさらなる加速:近年の改善を踏まえ、民間のスピード(市場の変化・資金のタイムスケール)により近づける運営を期待いたします。
- 橋渡しの強化:J-SPARCで芽吹いたコンセプト・技術が、政府の各種プログラムや民間資金へと切れ目なく移行するルートを一層強固にすることで、成功事例の連鎖を生み出せます。
5. まとめ(メッセージ)
日本の宇宙産業は、確かな技術力と海外からの厚い期待を背景に、いままさに外へ打って出る段階にあります。官と民、そして大企業とスタートアップが役割を持ち寄り、J-SPARCを要にした好循環を加速させることで、2030年代を振り返ったときに「いまが転機だった」と語れる未来を切り拓けると考えます。

第4章 新規事業家&投資家から見たJ-SPARCの価値
セッション概要
本セッションでは、JAXAの外側からの視点でJ-SPARCの意義と今後の伸びしろを議論しました。モデレーターはフォーブスジャパンWeb編集長の谷本 有香様、パネリストは新規事業家の守屋 実様、Frontier Innovations株式会社 代表取締役社長の西村 竜彦様です。J-SPARCが生み出した成果を踏まえ、次の成長段階に向けた「第二創業」の視点や、社会実装・認知拡大の打ち手を中心に意見が交わされました。
モデレーター
- 谷本 有香 様(Forbes JAPAN WEB編集長)
登壇者の自己紹介と立場
- 守屋 実 様(新規事業家): 企業内・独立・週末起業を横断して多数の新規事業を経験し、「新規事業家」を標榜して活動していらっしゃいます。宇宙は「地球外に広がる新市場」であり、新規事業の最前線として強い関心を寄せていると述べられました。
- 西村 竜彦 様(投資家): ソニーでの商品企画・新規事業を経て、政府系ファンドで宇宙ベンチャー投資に従事し、現在はディープテック特化ファンドを運営していらっしゃいます。上場企業を含む多数の宇宙スタートアップを支援してこられました。
外部から見たJ-SPARCの価値
- ユニークさと実効性: 公的機関であるJAXAが、オープンイノベーションで短期間に具体的成果を積み上げてきた点を高く評価されました。数字で可視化された成果は、純民間の挑戦にも強い動機づけになると指摘されました。
- 扉を開く役割: J-SPARCが幅広いテーマを受け止める「入口」になり、官公庁・大企業・投資家に連なる連携機会を創出している点が強調されました。具体例として、地方発ベンチャーの台頭や、社内プロジェクトのカーブアウト事例が挙げられました。
成功を支えた要因
- 「この指とまれ」を掲げる人の存在: 最初に旗を振り、起点となるJ-SPARCプロデューサーの熱量とコミットメントが、連鎖的な協力と資源流入を生みました。
- 熱量の掛け算: 技術者・経営者・支援者の熱が重なり、難易度の高い宇宙領域でも推進力が生まれたことが成功要因と整理されました。
今後の課題と「第二創業」
- さらなるスピードと引き継ぎ: これまで7年間の立ち上げの熱を保ちつつ、次に向けて、体制の世代交代・多様化を通じて熱量を継承・増幅させる必要があると指摘されました。
- 総力戦の深化: 企業家・JAXAプロデューサー・大企業・省庁・投資家が役割を持ち寄り、「使えるものはすべて使う」姿勢でレバレッジをかけていくことが提案されました。
関係人口を増やすために
- 非宇宙分野の参画: 宇宙は既に日常インフラです(測位・通信・観測等)。防災・インフラ維持管理・サプライチェーン最適化など、足元の課題解決に直結するユースケースを起点に、非宇宙企業の参画を広げられます。
- 2C文脈・エンタメの活用: AR、位置情報ゲーム等の身近な体験を通じ、宇宙由来技術の価値を個人レベルで実感できる設計が有効です。J-SPARCで立ち上がったエンタメ、フード、ヘルスケア、ライフ領域のプロジェクト拡張が期待されます。
- 教育・文化との接続: 子ども・学生を「チーフ・アイデア・オフィサー」として巻き込み、文化・伝統芸能との融合(例:無重力表現、月光照明の舞台演出等)に挑戦する発想が共有されました。
- 発信の仕組み化: デジタル上の“ホットスポット”を作るため、登壇者・参加者・視聴者がまず一投稿することから始め、連鎖的な発信を促すことが提案されました。リアルの展示・イベント参加とオンライン投稿の往復で熱の面を広げます。
投資・金融の観点
宇宙データやインフラの新たな資金循環(例:データの証券化等)への期待が示されました。企業は自社リソースの一部を外部連携に振り向けるだけでも、スタートアップの成長に大きなレバレッジを与えられると述べられました。
クロージングメッセージ
西村様: J-SPARCの継続と発展、そして半歩でもいいから踏み出す行動が重要だと呼びかけられました。
守屋様: 受け取った刺激は「やらない理由」ではなく「一歩の行動」で返すべきだと強調され、まずは全員で発信し、熱を次の人へ渡そうと締めくくられました。
本セッションは、「祭りは見ているより参加したほうが楽しい」という合言葉のもと、誰もが当事者となって熱量を伝播させる実践の第一歩を示した時間となりました。

第5章 異業種連携が生む事業化――ソニー×バスキュール×ミラツク×JAXA
セッション概要
本章では、異業種連携から生まれる事業化のリアルと今後の展望について、ソニーグループ株式会社・中西 吉洋様、株式会社バスキュール・朴 正義様、NPO法人ミラツク・西村 勇哉様、そしてJAXA/J-SPARCプロデューサーの藤平 耕一が語った内容を整理いたします。会場の熱量をそのままに、実践知として読み解きます。
登壇者とJ-SPARCとの関わり
- ソニー 「STAR SPHERE」
JAXAサポートの元、東京大学と共同で超小型衛星を設計・製造・運用し、ソニーのカメラで撮影・配信まで一気通貫で実施しました。運用は約2年間、撮影は約3,000枚。一般の方々(学生・社会人・子どもたち)延べ約500名が“宇宙にある衛星を自分で操作して撮る”体験を実現しました。現在は、油井宇宙飛行士の撮影写真を**「Earth Diary」**で追体験できる仕組みに発展させています。
- バスキュール「宇宙エンタメ/90分の地球一周ライブ」
国際宇宙ステーション(ISS)の周回に合わせ、観客が90分で地球一周をライブ体験する企画を多数実施。きぼう日本実験棟の継続利用、ARで地球上にデータを重ねる独自技術で特許も取得。直近の万博会場では各回2,000人×3回=約6,000人を動員、多くのイベントでオンライン視聴は100万規模に達する。
- NPOミラツク
企業の新規事業・経営戦略を“知識と情報”で伴走支援するリサーチ集団としてJ-SPARCに参画。宇宙での生活課題の可視化(例:無重力下の制約、宇宙飛行士の困りごと)、衛星データの種類と使い道の整理など、非宇宙企業が参入しやすくなるツール群を整備しました。J-SPARCの「ライフストーリーブック」にも知見が反映されています。
立ち上げのリアル(はじめの一歩)
- ソニー:最初は「宇宙やりたいよね」から始まった“有志の芽”。社内外へ100回規模のプレゼンを繰り返し、共感者を増やして前進しました(アイデアコンテストでの落選も糧に)。
- バスキュール:コロナ禍での決断「ハードを作らない」。既存設備とソフトウェアで価値提供へ最短到達し、J-SPARCや放送・省庁との連携で初速を上げました。
- ミラツク:参入障壁を下げるための基礎知の整備と、企業へのひたすらな電話・対話。宇宙×生活領域(Think Space Life)で“地上のニーズ”を宇宙技術に結びつけました。
コツ:社内稟議では**「JAXAと併走」**という信頼を適切に活用(社外表記はルール順守)。“人と熱量”が最初の推進剤です。
今だから話せる「想定外」と乗り越え方
- ソニー:衛星の姿勢制御機能に問題が生じ、自由な撮影が困難に。「一般の方に宇宙撮影体験を届ける」という原点に立ち返り、東大・関係者と改善。状況はできるだけ正直に発信し、共感と支援を得ました。
- バスキュール:ライブ中の不確実性と常に隣り合わせ。ISSの計画変更等にも即応。国際機関との連携調整、宇宙飛行士との現場最適化を積み重ねました。
- ミラツク:JAXA側の人に紐づく知が大きいため、異動で継承が難しくなる課題を実感。ナレッジの形式知化・引き継ぎ設計の必要性が教訓になりました。
異業種連携を加速する実践知
- 最短価値から始める:ハードに固執せず、既存資産×ソフトで初速を出す。
- toC視点を入れる:誰もが参加できる体験(VR、初日の出ライブ等)で“身近な宇宙”へ。
- 掛け算を設計する:宇宙×文化・教育・防災・ヘルスケアなど、用途起点で合意形成。
- 信頼のレバレッジ:JAXAの専門性とプロデューサーの伴走で、社内外の不確実性を抑制。
ハイライト(数字で見る)
- STAR SPHERE:運用約2年/撮影約3,000枚/延べ約500名が体験。
- 宇宙エンタメ(バスキュール):主催・提供あわせ十数回実施/万博約6,000人来場/オンライン100万規模視聴。
- Think Space Life:生活課題・衛星データ活用の可視化ツール整備、企業連携の基盤化。
これからの展望
- 宇宙が“特別な仕事”でなくなる未来へ:インターネットが生活に溶けたように、宇宙はインフラとして産業と日常を底上げします。
- ソニー:プロジェクトは休止中=再始動の余白。光通信やエンタメ等での再挑戦に意欲。
- バスキュール:国内実績を軸に海外展開と事業会社化を検討。200超の国・地域でスケールを狙います。
ミラツク:時代は**“Space × ○○”**。参入のしやすさが格段に向上。次の10年は用途主導での価値創出が鍵になります。
読者へのメッセージ
- 一歩目は人と熱量です。まずは社内外に100回伝える覚悟で動き、仲間と“共犯関係”をつくりましょう。
- 体験は共有してこそ価値が増幅します。イベント参加・SNS発信で、熱を次の担い手へ手渡してください。
- 必要ならJ-SPARCプロデューサーも稟議の同席などで伴走します。遠慮なく声をおかけください。
祭りは“見る”より“参加する”ほうが楽しいです。次の出番は、あなたです。

第6章 軌道上サービスが拓く“循環する”宇宙インフラ
セッション概要
本章は「今なら話せるJ-SPARC舞台裏2:軌道上サービス編」。アストロスケール・加藤 英毅様、株式会社BULL・宇藤 恭士様、Pale Blue・浅川 純様、モデレーターはJAXA/J-SPARCプロデューサーの市川 千秋が、軌道上サービス(On-Orbit Services; OOS)の現在地と実装戦略を語りました。OOSは、打上げ後の宇宙機に対して近接・把持・補給・修理・処分などの“アフターサービス”を提供し、宇宙産業を使い切りから循環型へ転換させる中核機能です。スペース・サステナビリティの鍵として、宇宙外の業界からの関心も急速に高まっています。
登壇企業のアプローチ
- アストロスケール(加藤様)
- 近接・ドッキング技術を基盤に、大型デブリ接近実証(CRD2)を実施。今後は捕獲へ推進。
- 燃料補給では、低軌道向け化学推進の補給を目指す国家プロジェクト(通称Kプロ)が始動。
- 売上は5年前の約4〜5億円 → 現在100億円超へ、受注残も数十億 → 450〜500億円規模に拡大。世界の競合は100社超に増加し、市場の「通り」が形成されつつあるという実感を共有。
- ビジョン:2030年にOOSを“日常のインフラ”に。
- BULL(宇藤様)
- デブリ発生防止に特化。ロケット上段や衛星に膜状デオービット装置等を事前搭載し、確実に落下させる「エアバッグ」的コンポーネントを開発。
- J-SPARCで上段部搭載シナリオを検討。日テレ連携の広報企画で社会浸透を促進。
- 本社は栃木県宇都宮市。「宇宙の宮」を商標化し、産学官金+地域ものづくりで産業拠点化を推進。欧州ではArianespace/AVIO等と実装連携を推進。
- Pale Blue(浅川様)
- 衛星用推進機(スラスター)を製造・提供。最小は手のひらサイズ(約10×10×5cm)から、近年は大型衛星向けまで拡大。複数機が既に宇宙で稼働中。
- J-SPARCで、JAXAの電気推進系知見(例:小型タンクの小型化技術)の導入と、大型電気推進の製品化に向けた共創を推進。
- 柏キャンパス発の開発・製造体制を整備し、「宇宙のモビリティ」を支える標準部品の社会実装を加速。
「市場はあるのか?」をどう越えたか
- 立上げ初期はデブリ=コストセンターの先入観から、需要を疑問視する声が多かったものの、CRD2での実機接近と補給の事業化筋が見え、
- 観測/補給/防衛転用/修理・延命など複線的な用途が顕在化。
- いまや“同じ場所に店が並ぶ”=市場が人を呼ぶ段階に。J-SPARC発の検討が複数の公的プロジェクトへ接続され、案件・資金が回り始めました。
共創(J-SPARC)が効いたポイント
- フェアな立ち位置:片務的な委託ではなく、双方が持ち出し・知見を出し合う設計。短期リターン偏重に陥りにくく、研究と事業の“真ん中”を進められる。
- IPと自社案件性:自己負担を伴う共同実証は、自社プロジェクトとして語れる。PR/説得力/社内稟議の通りも向上。
- 開発に不可欠な検証設備を整備:JAXAの研究開発部門と協力し、共通的な検証設備を整備。開発の加速化に貢献。
- 信頼のレバレッジ: 認知の立上げ期に「JAXAと何をやっているか」は強い信用の足場に。
- 地域連携(自治体・地場メーカー)や海外展開の名刺代わりとして機能。
立ち上げ時のリアルと学び
- 売りながら作る/作りながら売る:需要を聴き、スコープをローリング。固定化せず、顧客の学習速度に合わせて更新。
- 規制・ルールメイクと足並み:デブリ防止は制度シグナルが市場形成の起点。国際連携と歩調を揃えつつ、速すぎず遅すぎずのタイミング設計が鍵。
- “技術だけに寄らない”ために:プロダクトの上流(衛星設計・運用設計)や利用設計まで踏み込み、コンポーネント→ソリューションへ。プロデューサーは目標値の共有と進行中の再定義を回す。
数字で見る現在地(抜粋)
競合状況:OOS関連企業は世界で100社超。
アストロスケール:売上100億円超、受注残約450〜500億円へ。
実証:CRD2でH-IIA上段に接近/燃料補給はLEO化学系の実装プロジェクトが始動、GEO電気推進も提案中。
Pale Blue:複数機が軌道上稼働、小型〜大型へラインナップ拡充。
Bull:上段部デオービット装置の搭載コンセプトをJ-SPARCで具体化、欧州打上げ事業者との連携を拡大。
次のチャレンジ(提言)
- 商用柱の確立(加藤様):
- 政府(非防衛)/安全保障に続く商用を太くするには、補給・修理を衛星ライフサイクル前提に組み込む設計が要。J-SPARC段階から技術×ビジネスモデルの同時設計に挑む。
- 日本発の“勝ち筋”を作る(宇藤様):
- ニッチでも世界一の尖りで外需を獲得。「日本がないと回らない」部材・装置を地域製造基盤とともに育てる。
- モビリティ視点での標準化(浅川様):
- 推進機単体の先へ。衛星設計・運用・補給連携まで視野に、使い勝手の標準を共創で磨く。
- スピードと継承(全体):
- 共創は速く・継続的に。人に宿る知を形式知化し、体制の世代交代でも力が落ちない仕組みを。
まとめ
1〜2年で輪郭が見えた市場に対し、OOSは“使い切り”から“循環”へ切り替える産業インフラになろうとしています。J-SPARCは、研究と事業の間隙を埋める実験場として機能し、実証→制度・基金→商用への橋渡しを加速してきました。次の一歩は、技術開発と同じ熱量でビジネス設計を前段から織り込むこと。宇宙を「作って終わり」から「運用し続ける」へ――その未来図を、いま皆で具体化していく段階です。

第7章 ホンダの挑戦:共創から自走へ――“再使用型ロケット”で輸送のボトルネックに挑む
セッション概要
登壇者:石村 潤一郎 様(株式会社本田技術研究所 宇宙開発戦略室 チーフエンジニア/プロジェクトマネージャー)
本章では、J-SPARCでの共創期を経て社内自走フェーズに入ったホンダのロケット開発を取り上げます。石村様は、自動車用エンジン/エネルギー・CN技術を経て約1年半前に宇宙領域へ。現在は再使用型ロケットプロジェクトの責任者として、「技術は人のために」というホンダの価値基準を宇宙輸送に適用し、リーズナブルでサステナブルな輸送の実現に挑んでいます。
ホンダの宇宙挑戦とJ‑SPARCの効用
- ホンダ技術研究所の役割:本体100%子会社として、既存にとらわれない成長の仕込みを担うR&D組織。
- 三本柱:①循環型再生エネルギーシステム、②宇宙ロボティクス、③ロケット(再使用型)。本章は③が主題。
- 起点は“やってみたい”:社内の一人の発案から開始。宇宙知見が乏しい出発点ながら、J‑SPARCで無知であるが故の突飛な検討にも「どう実現するか」を共に考えてもらえる伴走を得て、ロケット技術に取り組む基礎的な土壌が整った。 。
- 共創→自走:対話と検討を重ね、仲間と専門性を社内に集結。現在はホンダ内での本格研究として継続中。
目指す未来像:データ時代の加速を実現する
AI・データ活用が進むほど地上の再エネだけでは電力が不足する未来を見据え、宇宙側の資源・衛星活用を取り込んだ社会設計が不可欠に。鍵は、衛星の活用を拡大し続けるための安価で持続可能な宇宙輸送。ホンダは、ここを自社の強みで切り開く方針。
2019年〜:静かな活動から、2025年には6月の重要実証実験へ
- 立ち上げ:2019年末にプロジェクト化。社外に大々的に語らず、社内の他研究テーマと同様に、基盤技術をコツコツ構築。
- 次STEPへの展開可否を判断する統合試験(今期6月): 垂直上昇→上空でホバリング。
- 狙点着陸:目標から偏差37 cmで着地。
- ねらい:多くの要素を一挙に試し、「これができるなら次のスケールに移行できる」と社内判断できるような、中身の濃い試験をデザイン。結果は計画どおりで、次段階への進出を後押し。
- 副次効果:公開後の反響が大きく、社内の意気と外部期待の双方が上昇。
開発の要点(実践知)
- 価値基準の明確化:技術は人のために――を開発判断の軸に据える。
- 最小実装で判定:小さく作り、統合挙動(推力・舵・姿勢制御・誘導・着陸)を早期に確認。
- 共創で知を底上げ:黎明期はJ‑SPARCの専門家と基礎知の底上げ。以後は社内で自立した研究推進、必要に応じて再接続。
これからの論点
- スケールアップ:推進系・制御則・機体構造の拡張と安全性の担保。
- コストと再使用:輸送費低減のための再使用アーキテクチャと整備設計。
- 制度・安全:運用ルールと試験場整備。この観点についてはJ‑SPARCや関連する施策・制度と連携して実装加速も必要。
まとめ
ホンダは、再使用型ロケットを起点に「安価で持続可能な輸送」で宇宙活用のボトルネック解消を狙います。J‑SPARC期に培った共創基礎知見を土台に、個社での自立した研究開発で次の“良いニュース”へ――人のための技術を宇宙でも体現していきます。

第8章 宇宙データ×AI×広告――キャベツ価格を“見に行かずに”読む
セッション概要
登壇:北川 廣野 様(株式会社電通 データ・テクノロジーセンター/AI& テクノロジー開発部 シニアプランナー)、高橋 陪夫(JAXA 新事業促進部 J‑SPARCプロデューサー)
本章は、衛星データ × AI × 広告で農産物の価格変動を先読みし、販促の最適化と地域課題解決を同時にねらう取り組みの要約です。舞台は群馬県・嬬恋村(夏秋キャベツの国内シェア約7割)。広大な耕地をドローンでは把握しきれないという現場課題を、衛星画像で一気に把握するアプローチへ転換しました。
なぜ電通が宇宙?(発想の出発点)
- 仮説:キャベツの生産量が上がる → キャベツ価格が下がる →調味料等関連商材が売れやすくなる →広告を強化する。キャベツの生産量が下がる → キャベツ価格が上がる →調味料等関連商材は売れにくくなる →広告は抑える。
- 生育・収穫量の先読み → 価格の先読み → 広告出稿の最適化という連鎖を作ることで広告の最適運用が可能ではないか?
なぜ衛星?(スケールの壁)
- 嬬恋は面積が広く、車やドローンの巡回では面全体の把握が困難。
- 衛星なら嬬恋村のような広大なエリアを反復観測でき、現実的な人日で衛星画像分類モデル構築のためのデータが得られる。
座組み(共創体制)
- 電通:全体設計/広告活用・価格モデル設計/セールス。
- 電通デジタル:AIによる価格予測モデル構築。
- リモート・センシング技術センター(RESTEC):衛星データ解析、生育分類モデルの開発。
- 両毛システムズ:現地調査の効率化システム化、予測モデルの可視化ダッシュボード構築、地域連携のハブ。
- JA嬬恋村:現地ニーズ・運用・ドメイン知識共有・販促連携
- 群馬県:地域連携の後押し。
- JAXA/J‑SPARC:衛星利活用の設計・伴走(高橋)。
技術基盤と今年の進捗(2024)
- 現地データ:両毛システムズ開発のアプリにより一回の現地調査で約1,400点のグラウンドトゥルースを取得。
- 生育分類:RESTECが6段階の生育状況を識別する衛星画像の高精度分類モデルを構築。
- 収穫量推定:生育分類から収穫量の空間分布を推定。
- 価格予測:電通(電通デジタル)が市場価格モデルを構築済。
- 統合へ:上記2系統(収穫量予測 × 価格予測)を一体の価格予測システムに統合中。
フィールドワーク:我々チームは毎月嬬恋村の現地へ。 “キャベツと対話する”ルーティンでデータの質を底上げ。
地域創生と消費者コミュニケーション
- JA嬬恋村:衛星で圃場の生育を俯瞰→出荷計画の精緻化→価格の安定化に寄与。
- 販促施策:店頭で使う販促では史上初のJAXAコラボ販促アイコンを制作。来年度の小売展開を目指す。※嬬恋村公式マスコット「キャベツちゃん」の活用も案内。
- 地域産業×IT:群馬発のSI企業(両毛)と連携し、地場製造・ITの雇用・付加価値を地域に循環。
ロードマップ
- 今年:モデル統合の完了(生育→収穫量→価格の一貫推定)。
- 来年:クライアント参画で広告出稿の実証(需要期の“広告の強化”、高騰期の“広告の抑え”)。店頭販促アイコンの本格展開。
- 中長期:農業DXとして他の葉茎菜・根菜へ横展開/日本モデルの海外輸出を視野に。
実務で得られた知見(抜粋)
- 面で把握して面で動く:個別圃場の観察ではなく、産地全体の“面”で需給設計。
- ラベルの質が精度を決める:1,400点の現地調査データはモデル性能の鍵。
- コミュニケーション設計:生産(JA)→市場→小売→消費者の理解、生産の状況を把握することで、生産から消費まで一気通貫のコミュニケーションを設計が可能。“供給の“見える化”が需要を広げる。
成果指標のイメージ
- 生育分類精度、収穫量推定、価格予測。
- 販促のROAS改善、出荷の平準化、廃棄率の低減、物流の波の緩和。
まとめ
宇宙データを広告と結び、「地域課題の解決」と「商業の最適化」を同時に実現する挑戦が始まりました。J‑SPARCは、異分野の掛け算を促す実験場です。店頭でこのアイコンを見かけたら、ぜひ“恋するキャベツ”を手に取ってください。

第9章 パネル:宇宙で儲けよう――加速する新ビジネス
セッション概要
テーマは**「宇宙で儲けよう/加速する新ビジネス」。日本テレビアナウンサーの川畑 氏(モデレーター)の進行で、スペースタイド代表理事 石田 真康 様、Cチャンネル代表取締役社長/スペースデータ社アドバイザー 森川 亮 様、女優・気象予報士・防災士の武藤 十夢 様**が、宇宙ビジネスの現在地と“次の稼ぎ方”を多角的に議論しました。
登壇者
- 石田 真康 様(一般社団法人SPACETIDE代表理事 兼 CEO)
- 森川 亮 様(C Channel代表取締役社長/スペースデータ社アドバイザー)
- 武藤 十夢 様(女優・気象予報士・防災士)
- モデレーター:川畑 一志(日本テレビアナウンサー/日テレHR総合研究所 コンサルタント)
キーメッセージ
- 宇宙は夢ではなく現実:気象・測位・放送は既に日常インフラ。宇宙ビジネスは“宇宙業界の専売”ではなく、あらゆる業種が参入する時代へ。
- マネタイズの解像度が上がった:安全保障用途や衛星データ(観測・通信)など、短期で収益化しやすい領域が拡大。上場スタートアップも増え、一般投資家のアクセスも可能に。
- 越境がブレイクスルー:宇宙×ファッション/スポーツ/金融/農業など、“宇宙×◯◯”の掛け算が新市場を開く。J‑SPARCに期待される役割は、まさに越境の仕掛け。
主な論点(ダイジェスト)
1.メディアと認知の変化
- 10年前は取材も難しかったが、いまは毎日宇宙ニュースが流れる状況に。SNS・YouTubeでも情報量が急増。
2.いま儲かる・これから儲かる
- 安全保障×衛星データ:ウクライナ情勢でも民間衛星画像が活用。需要は継続的に拡大。
- リモートセンシングの応用:電波等の観測で**資源探査(例:鉱山の兆候)**まで読み解く可能性。センサーデータ由来のSaaS/インテリジェンスは有望。
3.宇宙を“行く”か、“作る”か
- スターウォーズ世代=物理的拡張(移住・月/火星)、マトリックス世代=デジタル拡張(デジタルツイン宇宙)。スペースデータ社は後者のアプローチで宇宙OS/ツインを志向。
4.宇宙×ファッション(武藤案)
- 宇宙素材の地上転用(断熱・防護等)は既に一部実装。民間旅行時代には機能+審美性の需要が拡大。無重力の“映える”演出で宇宙ファッションショー等の新体験も。
5.宇宙×スポーツ/エンタメ
- 無重力スポーツ(サッカー/格闘技/レース)でルールも身体性も再設計。地上操作×宇宙アリーナ(3Dプリンタ製機体・月面レース)など、eスポーツ的拡張の余地。
6.宇宙×金融・データセンター・保管
- 宇宙保管・宇宙倉庫のアイデア、月裏側等の電波遮蔽を活かした超高セキュリティのデータ保全、宇宙太陽光の利活用などエネルギー優位を活かす構想が議論に。
7.宇宙×農業・食
- 宇宙米/植物工場など、極限環境での食の自給に挑む動き。地上の気候変動リスクを回避した安定供給の可能性も。
8.マネタイズの難所と打ち手
- 資源・観光は王道の収益柱。制度面では宇宙資源法等で商取引の前提が整備。短期は安全保障・データ、中長期にインフラ・観光が拡大。
10年後の宇宙ビジネス(2つの世界線)
- A:部分最適の延長線……安保・政府需要は拡大する一方、民生・体験系は限定的。宇宙は“遠い”まま。
- B:民主化の加速……宇宙ホテル/月面滞在が現実に、宇宙渡航経験者が1万人規模へ。私たちの誰かが「行ってきた」と語る世界。
どちらに振れるかを決めるのは、圧倒的な牽引役(1〜2社)と、異分野の越境連鎖。
J‑SPARCへの期待とクロージング
- 越境のハブとして、宇宙⇄非宇宙の橋をさらに太く。ファッション/スポーツ/金融/食など“未接続の橋”を架けていく。
- 参加のすすめ:宇宙ビジネスは参入待ち。J‑SPARCは相談の入口であり、社内稟議を通すための信頼のレバレッジにもなる。
宇宙×◯◯の主役は“あなた”。10年後に「全員、宇宙に行った?」と笑い合える未来へ、次の一歩を。

第10章 日本橋が“宇宙共創の街”になるまで――三井不動産とJ‑SPARCの7年
セッション概要
登壇:七尾 克久 様(三井不動産株式会社 日本橋街づくり推進部長)
本章は、日本橋が宇宙プレイヤーの集う街へと変貌した軌跡と、これからの受け皿づくりを、まちづくり当事者の視点で振り返った講演の要約です。J‑SPARCの立ち上げ期から伴走し、“場”と“つながり”を積み上げてきた歩みが共有されました。
年表でみるエコシステム形成
- 1999–:官・民・地域一体となった日本橋再生計画が始動。直近10年は将来有望な産業を支援する「産業創造」に注力。
- 2016:ライフサイエンスのオープンイノベーションのプラットフォームLINK‑J設立。
- 2018:JAXAとの出会いを起点に、日本橋三越本店向かいの福島ビル内に「X-NIHONBASHI」を開設。“ビジネスマッチングにふさわしい場づくり”をゼロから共創。
- 2019:日本橋再生計画の記者発表で「宇宙×まちづくり」セッションを実施(スペースタイド・JAXA・ANA HDが登壇)。
- 2021:J‑SPARCから派生:X-NIHONBASHI Global Hubを立ち上げ、NASAアジア代表、スペースタイド石田氏、SpaceBD永崎氏ら国内外のキーパーソンと連携。
- 2021–2024:NIHONBASHI SPACE WEEKを4回開催。宇宙プレイヤーの“年次総会”として定着。
- 2022:宇宙産業支援の社団法人クロスユー設立。
- 2025/7:半導体産業支援の社団法人RISE‑A設立。宇宙×半導体×ライフサイエンスの産業を日本橋に集積。
- 現在:拠点はX‑NIHONBASHI TOWER/BASEの二拠点体制へ。日本橋における"宇宙のハブ”が定着。 日本橋での宇宙関連イベント累計 約1,200回に到達。
ハイライト:J‑SPARCとの連携により、宇宙産業における「人が集まり、知が重なり、次のビジネスが生まれる」循環が街の機能として実装。
J‑SPARCが果たした役割
- 入口の共創:門外漢だった不動産側に、テーマ設計・イベント運営・マッチング作法を一からインストール。
- 信頼のレバレッジ:JAXAと並走することで、企業や自治体、海外機関が集まり・動く。
- 継続の仕組み化:単発ではなく年次行事(NIHONBASHI SPACE WEEK)/常設拠点(TOWER/BASE)へ昇華。
数字で見る日本橋×宇宙
- LINK‑J:955会員 (2025年8月末時点)
- クロスユー:319会員 (2025年7月末時点)
- 宇宙関連イベント:累計 約1,200回
- NIHONBASHI SPACE WEEK:4回開催
これからの受け皿づくり(まちづくり×産業振興)
- 首都高地下化+日本橋川沿いエリアにて5つの再開発が進行。その内の一つ、日本橋一丁目中地区には、
- 約3,000人規模のホール、
- 商業施設・ホテル・サービスアパートメントを整備予定。
- ねらい:世界中の宇宙関係者を常時受け入れ可能なMICE拠点とし、展示・国際会議・実証・レジデンス(長期滞在)を一体運用。
今後のまちづくりの示唆(ポイント)
- 産業政策:研究・事業・資本・広報が偶然に出会える"場と機会"を設計する。
- 越境の積層:宇宙に加え、半導体/ライフサイエンスのハブを地理的に重ね、複合イノベーションを誘発。
- 形式知化:人に宿るネットワークや運営ノウハウを手順化・継承し、世代交代でも力を落とさない仕組みへ。
宇宙事業に関する今後の取組について
- J‑SPARC:NIHONBASHI SPACE WEEKを橋渡し装置として、制度・基金・海外接続へ切れ目なく連動。
結び
日本橋は、宇宙とは無縁だった街から、宇宙プレイヤーが集う街へ。次は世界の交差点として、日本発の宇宙産業を“街の力”で押し上げる段階に入ります。――「日本橋から宇宙へ続く道」を、皆で太くしていきましょう。
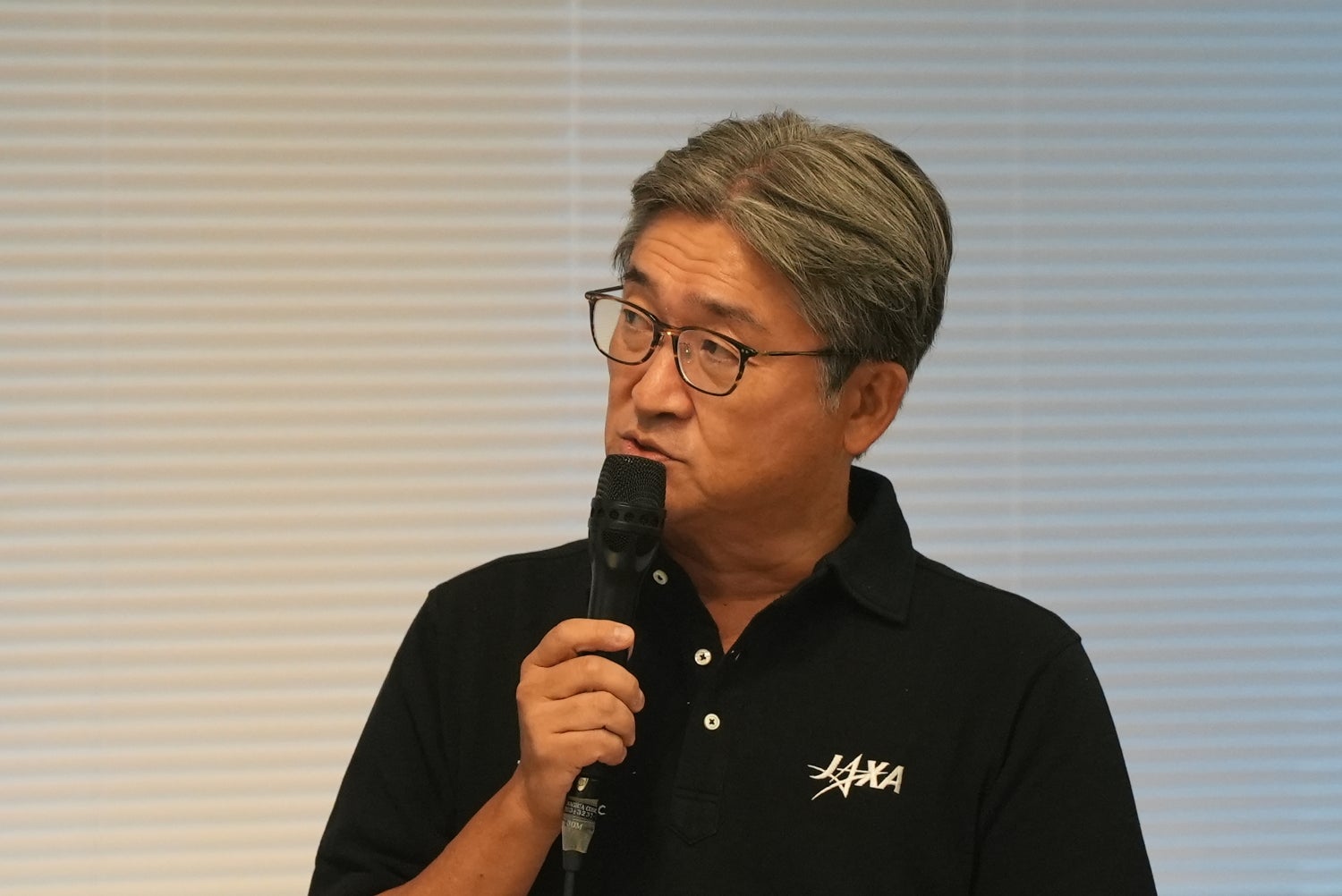
第11章 閉会のことば――「第二創業」へ、そして一歩を踏み出そう
セッション概要
登壇:内木 悟(JAXA 新事業促進部 部長)
内木部長は、本イベントを「J‑SPARCの振り返りと今後を建設的に議論する“祭り”」と位置づけ、意図的に“ぶっちゃけ”た議論を展開した理由を説明。ご自身も昨年6月に着任したばかりで、本日のセッションを通してJ‑SPARCの裏側や教訓を新たに学び、次に生かす示唆を得たと述べました。
キーメッセージ(要約)
- 率直な共有の効用:成功だけでなく「何が起き、どこに苦労があったか」を共有することが、次の挑戦者の資産になる。
- “宇宙で儲けよう”を真面目に:数年前なら笑われたテーマが、いまは正面から議論できる段階に。考える人が増えれば世界は変わる。
- 世代継承としての「第二創業」:創業者が築いたものを引き継ぐ側が磨き直す責任。自身も“刺さった”言葉として心に刻み、体制の再設計と継承に向き合う決意を表明。
- 体験が価値観を変える: 「一人ひとりが宇宙に行くと何かが起こる」という視点に共感(“スターウォーズ世代”としても)。宇宙の民主化を進めたい。
- 発信は参加:本会終了後、まずは全員が1投稿。オンラインの連鎖で熱量を広げる。
行動の呼びかけ
- J‑SPARCを“場”として使ってください:制度・仲間・知見を梃子に、ぜひ参画と第一歩を。JAXAも伴走を続けます。
- 感謝と謝意:会場・オンラインの参加者、登壇者、関係者すべてに謝意を表し、閉会を宣言。
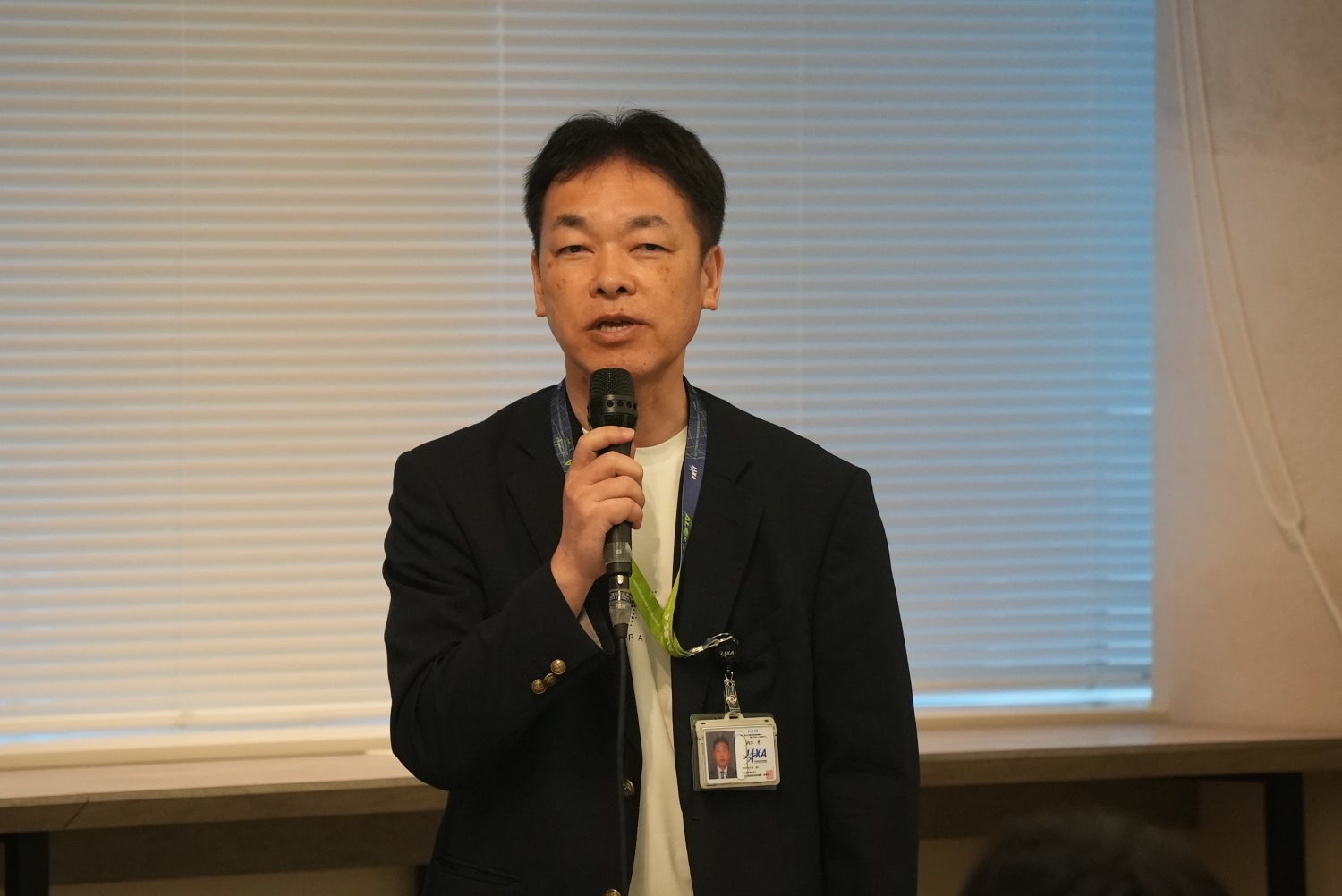
付記:クロージング
司会より、「以上をもちまして『J‑SPARC祭り2025』は閉会」との案内があり、会場・オンライン双方へ謝辞が述べられました。
これからもJ-SPARCをよろしくお願いします!

行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ




















