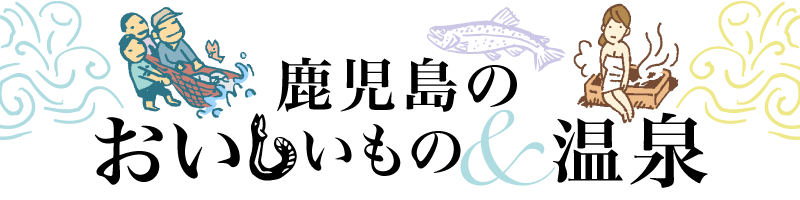左から時計周りに「しょうゆ」「きなこ黒糖」「みそ」
鹿児島県民にとっておなじみの郷土菓子・両棒(ぢゃんぼ)餅。名前の由来は、2本の竹串が刺さったその姿だ。

焼いた餅に2本の竹串を刺して保温器の中へ。たれになじませる
中国語読みで「りゃんぼう」と呼ばれていたものが少しずつなまり、「ぢゃんぼ」となったという。両棒餅の歴史を教えてくれた仙巌園の学芸員・岩川拓夫さんによると、
「当時の鹿児島の人は『らりるれろ』の発音がうまくなく、『だぢづでど』になってしまっていた」
のだそう。
もともと江戸時代に鹿児島市の慈眼寺地区で作られ始めた両棒餅。明治になり、島津家に仕えていた人が磯で店をはじめたことをきっかけに、磯の名物となった。

両棒餅と書いて「ぢゃんぼもち」と読みます…時代劇に出てきそうな雰囲気
国道10号が開通し、姶良まで歩いていた人たちが休憩する際は、お茶菓子として人気を集めたそうだ。令和の現在でも磯海岸近くの道路沿いには両棒餅店が数店舗並び、鹿児島県民の思い出の味を守っている。

両棒餅店が立ち並ぶエリアはココ
仙巌園内「両棒餅屋」では、両棒餅をより身近に感じてもらおうと2022年3月から両棒餅を焼く体験を始めた。

仙巌園「両棒餅屋」にて。もち米を炊いてついた100%もち米の餅を機械で成型し、鉄板で焼く。焼く際は膨らみ具合などを確認しながら。少し焦げ目を付けるのがポイント
店員にアドバイスをもらいながら餅を焼き、体験のみの味付けといういそべ餅風でも食べることができる。友だち同士やカップルで、孫と一緒に、など楽しみながら作った両棒餅のおいしさは格別。鹿児島の歴史に触れる機会としてもうってつけだ。

仙巌園 両棒餅屋

島津家別邸 名勝「仙巌園」入口