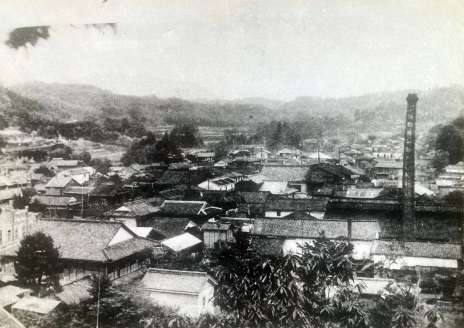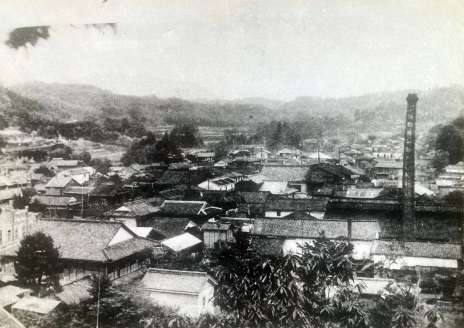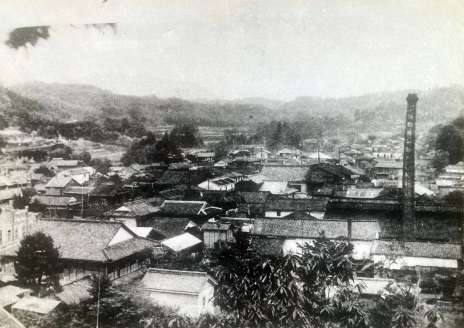
戦前の岩川市街地。岩川醸造のレンガ造り煙突に空襲警戒用の監視所が設けられていた(澤さん提供)
■澤俊文さん(83)鹿児島県曽於市大隅町岩川
1945(昭和20)年8月6日、岩川町(現曽於市大隅町岩川)市街地は、米軍空襲に遭った。
父・貫一と母・カスミが営んでいた木造2階建ての写真館は、国鉄志布志線岩川駅近くで現在、鹿児島銀行岩川支店が建っている場所にあった。
4歳の私は、この日の正午すぎ、隣家の桑原病院の娘で幼なじみの桑原和子さんと写真館1階にある8畳間でかるた遊びに興じていた。隣の6畳間には、末吉高等女学校4年生だったいとこの二木雪子が、体調不良で学校を休み、寝ていた。
近くの岩川醸造敷地に立っていたレンガ造り煙突の上には、空襲警戒用の監視所があり、監視員が詰めていた。「敵機来襲ー」。監視員がメガホンで叫んだ瞬間、「バリバリ」というごう音とともに、窓ガラス数枚が砕け、体の左側の畳が「ブシュ、ブシュ」と音を立てて波打った。米軍機の機銃掃射だった。
いとこが「撃たれたー」と叫び、ふとんからはってきた。弾丸の砕けた破片がかかとの肉をそぎ取り、血まみれだ。破片は、2階スタジオに置いてあった大型カメラにも食い込んでいた。
何が起こったか理解できなかったが、ごう音といとこの出血に、恐怖を感じた。両隣の家と合同で設けていた防空壕(ごう)に家族で逃げ込んだ。壕には地下水が30センチほどたまっていた。20メートルも離れていない岩川駅では、待合室にいた3人が撃たれて亡くなっていた。米軍機は岩川駅を狙ったのだろう。
いとこは歩けるようにはなったが、完治には戦後、かなりの期間を費やした。
空襲から間もない日に、母と列車で都城市に向かった。母と私は目が悪く、市役所近くにあった眼科医院に定期的に通っていた。
途中の今町駅で一時、列車を降ろされるなど、空襲警戒は続いていた。到着した西都城駅では、帰りの切符を買うために窓口に並んだ。母と2人、列に並んでいると、「ジャー」「ドカーン」という、爆弾ようの何かが落ちてきてさく裂する音がする。「空襲だ。伏せろ」と声がかかり、地面に伏せた。
駅を出て、国道10号沿いの高野薬局に写真現像液を買いに行った。不快な音は断続的に続いていて、薬局では、従業員とともに蔵にしばし避難させてもらった。
眼科医の診察を終えた後、どういう理由かは分からないが、母は西都城駅近くの病院に立ち寄った。病院に入ると、空襲被災者とみられる、血まみれになった人々が床にずらりと寝かされていた。
失礼ながら、手足を失ったけが人が幽鬼のように見え、私はすっかり震え上がってしまった。夜、寝入る前にその光景が頭に浮かび、しばらく、便所に行くのも怖かった。
あれから79年になるが、4歳の頭に刻まれた戦争の記憶はわずかながら今なお鮮明だ。でも、その記憶があったからこそ、芙蓉(ふよう)部隊や幕末の戊辰戦争に岩川から出兵した私領5番隊など地域の歴史に興味を持ち、追い続けてきたように思う。
【メモ】岩川への空襲は1945年8月6日、都城大空襲に参加した米陸軍航空隊のP47戦闘機隊の一部が、沖縄基地への帰還途中に行ったものとみられる。同日以降の都城盆地への空襲については、市史などに具体的記述はないが、豊の国宇佐市塾(大分県宇佐市)が入手した米軍資料には、8~10日、鉄道施設などに米陸軍航空隊が小規模な空襲を行ったという記録がある。
(2024年8月16日付紙面掲載「写真館の一人息子㊦」より)