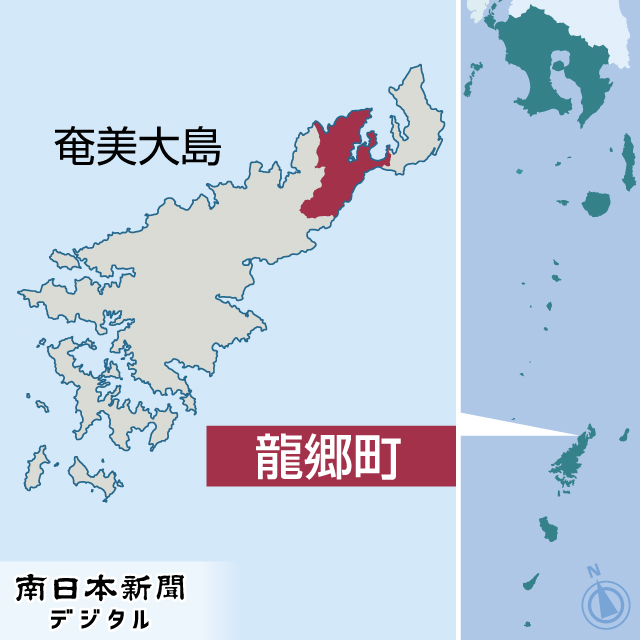リモートでインタビューに答える帝京大学の浜井和史准教授=鹿児島市の南日本新聞会館
〈戦後76年 遺骨は語る〉受動的で消極的「グランドデザインなき日本の遺骨収集」 帝京大・浜井准教授インタビュー
2021/08/19 11:00
-国の遺骨収集事業をどう評価するか。
「76年通じて場当たり的。一貫したグランドデザインがないままずるずる過ぎた。厚生労働省の援護政策の枠組みで遺族の心情をどう慰めるかの観点から進められ、受動的、消極的に進めてきたのが特徴。『国の責務』『責任』とその時その時で唱えるが、どこかで区切りを付けようとし、その度にまた見つかるという繰り返しだ」
-なぜそうなった。
「そもそも非常に膨大な戦没者が海外に取り残され、ジャングルなど過酷な戦場で戦後何年もたってから捜索するのは難しい。早い段階で、どう適切に処理すべきか考えるべきだった。1950年代の事業開始当初から全ての収容を諦め、いったん終了とした影響も大きい」
-長く戦没者の身元特定も消極的だった。
「当初から、誰の遺骨で遺族に返さねばという強い意識が欠けていた。日本人の誰かという意識が低いので、他の国籍かもという考えにはほとんど及ばなかった。現地で見つかった遺骨を現地で火葬し、日本人かも分からないまま持ち帰る状況を続けた」
「2000年代に入ってDNA鑑定が導入され、科学的手法で個体識別が始まると整合性がとれなくなった。当初はごく少数しか鑑定にこぎ着けず、問題が表面化しなかった。多くの検体が鑑定されるようになり、今までのやり方のまずさが明らかになった」
-遺骨の多くが無縁仏として扱われたことで生じた影響は。
「戦後の日本社会が戦争責任の問題に向き合う重要な機会を失うことにもつながった。戦争の記憶継承は大きな課題だが、日本の戦争記憶や平和学習は、原爆や空襲など国内の被害のことが目立つ。遠く離れた地で激戦があり、多くの兵士が飢え死にするなど無残に倒れ、大勢の現地の人も傷つけたという想像力が欠けていた。そういう記憶の継承が追求されず、戦争責任の議論も内向きになった」
-今後どうしていくべきか。
「膨大な遺骨が残る現実があり、打ち切れないだろう。ただ遺族でも継続すべきか否か意見は割れる。高齢化で続けるべきとの声は減っていくが、それでやめていいのか」
「戦没者遺骨収集推進法の集中実施期間が終わる頃までに、新しい時代の積極的意義付けを、遺族やそうでない人、若い世代などからさまざまな意見を募り、考えるべきだ。収集に参加した学生ボランティアは現地で戦争のリアルを目にし、意識が変わる。まさに一片の遺骨は語っている。海外戦没者の存在は考える機会につながる。広く社会に知ってもらうことも大事だ」
はまい・かずふみ氏 1975年北海道生まれ。2004年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程指導認定退学。外務省外交史料館勤務を経て現職。