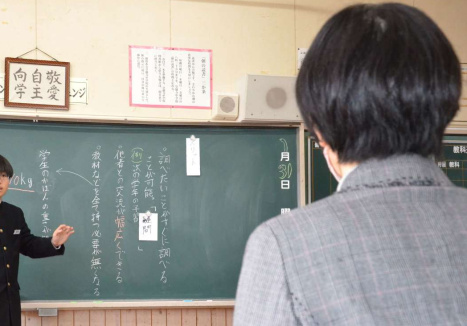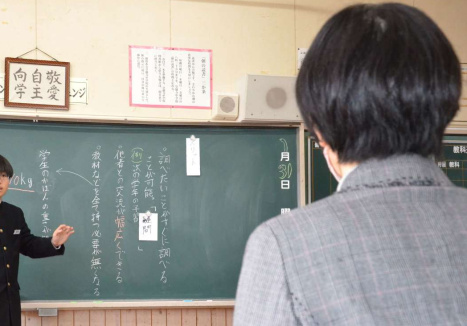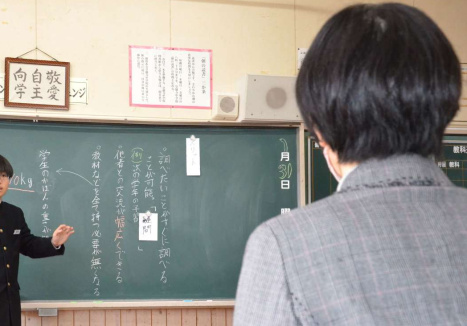
自己推薦入試を控え、プレゼンテーションの練習に取り組む生徒と進路指導主任の教諭=3日、鹿児島市の皇徳寺中学校
公立高校への出願者数が低迷する中、鹿児島県教育委員会は2025年度の推薦入試から、生徒自らの意思で出願できる自己推薦方式を導入した。4日に行われた推薦入試の出願者は従来の学校推薦611人に対し、自己推薦は681人。平均倍率は24年度の0.28倍から0.49倍に急伸した。受験者や学校関係者から歓迎の声が挙がる一方、学力低下などへの懸念も出ている。
「進路を実現するチャンスが増えた」。鹿児島市の男子中学生は4日、一般入試も出願する志望校の自己推薦を受験した。バスケットボールクラブで全国大会に出た実績をアピールし、面接に臨んだ。
自己推薦は、従来の学校推薦で評価される生徒会活動や部活動に加え、校外での活動も対象となる。習い事や資格取得などに励んだ生徒には門戸が広がる。男子中学生は「自分の強みを深く考える機会にもなった」と満足する。
■利点と課題
各高校は自己推薦導入の出願資格や選抜方法をそれぞれ設定した。鶴丸(鹿児島市)は、世界大会代表や全国入賞程度の実績といった基準を設定。鹿児島玉龍(同)のように専門分野の実技や作文など、試験内容を変えた学校もあった。
武岡台(同)は今回、自己推薦のみ実施。プレゼンテーションを試験に追加した。しかし、出願者は前年度から4人増にとどまった。亀田誠校長は「なじみがない試験に戸惑った受験生もいたはず。今後は中学校と連携しながら、制度の浸透を図るとともに、試験内容も見直していきたい」と課題を挙げた。
送り出す中学校側には温度差もある。11人が自己推薦を出願した皇徳寺中(同)の山下久美子校長は「学校外での、生徒の幅広い活動が生かされる」と評価する。一方で、別の校長は「活動を重視し、勉強をおろそかにする生徒が増えないか」と危惧する。
推薦入試の受験者増や、選抜方法の多様化による現場の負担も大きい。皇徳寺中進路指導主任の教諭は「生徒にとってはいい制度だが、志望理由書の添削や面接指導をするのは大変」と明かす。
■ルール
全国的に導入が進む中、学力や教員の負担を考慮した取り組みを進める自治体もある。宮崎県教育委員会は22年度から、県立高の学校推薦を廃止。提出書類など事務手続き軽減を図る。
また、自己推薦の導入校は原則、学力検査を実施する。県教委の担当者は「学力を基盤に、生徒の特徴も尊重した総合的な選抜を行うよう呼びかけている」と説明する。
高校教育に詳しい上智大の相澤真一教授(教育社会学)は自己推薦について、「志望校の校風や教育課程と自分の個性を照らし合わせて受験するため、理想の進学先にマッチングがしやすい」とメリットを挙げる。一方で、試験内容や評価基準の設定が各校に委ねられている現状は「学力や公平性を担保するため、一定のルールが必要」と指摘した。