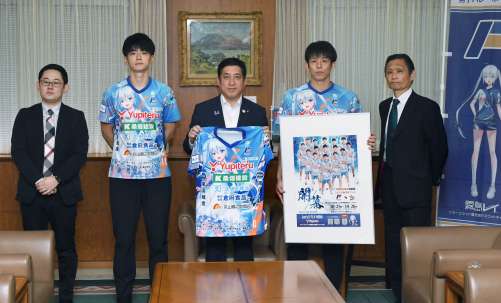日本一を記念し開かれた感謝祭【預S注意】。いかに消費を伸ばすかが鍵となる【預E注意】=3月29日、鹿児島市(佐伯直樹撮影)
急須でお茶って面倒くさい? 食卓から消えゆく習慣、どうしたら取り戻せるか…茶産地日本一の真価が問われるのはこれからだ
2025/04/05 20:45
「荒茶生産量日本一はうれしいが素直に喜べない」「鹿児島のお茶がどう生き残っていくのか、今こそ真剣に考えるべきだ」-。3月26日、2025年産茶の出荷対策会議に集まった茶業関係者からは厳しい言葉が相次いだ。
ペットボトル茶の登場や嗜好品(しこうひん)の多様化で急須離れが言われて久しい。総務省家計調査によると、全国の2人以上世帯が24年の1年間に購入した緑茶の茶葉(リーフ茶)は平均で671グラム、3194円だった。10年で2割強減った。
好調な有機栽培茶やてん茶は、まだ一握りに過ぎない。主力であるリーフ茶向けの一番茶価格は低迷する。県茶市場で取引された24年産の一番茶本茶の平均単価は1キロ当たり1827円。30年ほど前は3000円を超えていた。
肥料や人件費などコストはかさむ一方だ。県茶生産協会の田原良二会長(65)は「茶価が上向かないと後継者も育てられない。離農に歯止めをかけるためにもリーフ茶の消費拡大は重要」と強調する。
■非日常
手をこまねいてきたわけではない。茶価低迷を機に、県は09年度から県内小学校高学年を対象にお茶の入れ方教室を続ける。未来の消費者を見据えた取り組み。これまで延べ11万人以上が受講した。家庭でも楽しめるように、10~22年度は受講児童全員に急須と茶葉をプレゼントした。
ただ鹿児島市のリーフ茶の年間消費額は22~24年は平均4384円で、県庁所在地などの中で全国8位。トップの静岡市の半分程度しかない。
お茶の研究や普及に力を入れる鹿児島県立短期大学生活科学科の木下朋美助教(47)は「お茶を入れることは日常ではなくなりつつある。いきなり急須に回帰させるのはハードルが高い」と指摘する。
講義でアンケートを採ると、急須で茶を入れる学生は4分の1程度しかいない。茶葉の量や湯の温度など、おいしく入れるためのひと手間を煩わしく感じているようだ。
そこで木下さんは水出し緑茶を積極的に勧めている。「苦みや渋みが出にくく、はまって毎日飲む学生もいる。手軽な飲み方を入り口に、徐々に急須で入れるお茶へ移行してもらっては」と提案する。
■簡便さ
生活様式が変化し、簡便さは一つのキーワードになる。県大隅加工技術研究センターが開発したフリーズドライ茶は新たな一手になりそうだ。
お茶を真空凍結乾燥させて固形にする技術で、今年特許を取得した。お湯や水にサッと溶けて茶殻も出ない。既に数社が商品化している。
大橋製茶(鹿児島市)の大橋直社長(58)は「急須で入れた一番茶のおいしさを再現できる。需要創出の突破口になるのではないか」と期待する。粉末状に加工して個包装した試作品を作り、ホテルや高級料亭でウエルカムドリンクなどに使ってもらえないか売り込みを図っている。
少子高齢化で国内市場は先細りし今後、海外が主軸となっていくだろう。一方で、国内にも新たな需要開拓の余地は残っている。新茶のシーズンが間もなく始まる。日本一の茶産地の真価が問われるのはこれからだ。
=おわり=