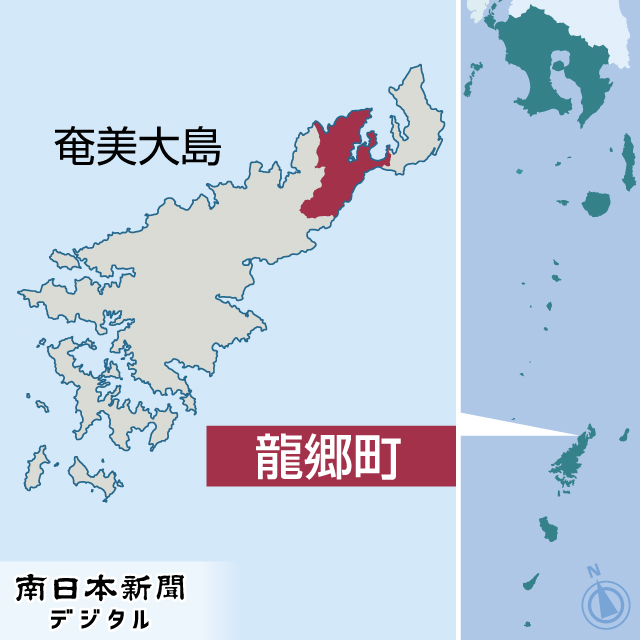公益通報の窓口を紹介する鹿児島県警のホームページ
「公益通報制度の〝隙〟に落ちた」――逮捕された〝告発者〟県警元部長。識者は刑事裁判の行方を「重要な判例になる」と注視する
2025/05/19 06:03
組織の不正を訴える通報を巡り、議論を呼んだ事例は数多くある。2000年代は牛肉産地偽装や車のリコール隠しなどが内部告発によって明るみに出た。説明責任やガバナンス(組織統治)への意識の高まりもあって、「公益通報者保護法」は06年施行された。通報者だけでなく、消費者の利益保護という観点が立法の出発点となっている。
公益通報は、労働者などが勤務先での一定の法令違反行為を通知することをいい、自らが利益を得るなど不正の目的がないことも要件になる。
保護法は(1)内部通報(2)行政通報(3)マスコミなどへの通報-の三つに分類している。マスコミなどに持ち掛ける外部通報は、真実と信じるだけの相当な理由「真実相当性」を必須とし、内部通報と比べると保護の条件が厳しくなる。
■ □ ■
鹿児島県警にも通報窓口はあるが、元生安部長はそれを活用せず、札幌市のフリーライターに文書で不祥事を訴えた。
県警はホームページで「内部公益通報等を受け付けています」と明示している。県警によると、窓口は監察課が担う。外部に通報する場合は、県警を介さずに法律事務所や県公安委員会と直接やり取りできる方法を設けている。
通報手段は郵送のほか、電話やファクス、電子メールがあり、匿名でも受け付ける。監察課は「通報者の意向に応じて匿名を守り、担当者には守秘義務を課すなど、通報者の不利益にならない体制を整備している」と説明する。
元生安部長は県警の制度を使わず、なぜマスコミへ通報したのか。これまで本人は言明していないが、鹿児島地裁での裁判手続きでは「定年退職する時期になっても不祥事が公表されることはなかった。(中略)マスコミが記事にすることで、明らかにできると思った」と述べている。
■ □ ■
元生安部長の行動は公益通報なのか。制度に詳しい淑徳大学の日野勝吾教授は「個人情報を外部に持ち出した重大さと、行為がもたらす公益性を比較し、一連の行動を公益通報の一環だと裁判で認定されるかどうかが焦点だ」とみる。
ただ公益通報は、通報を理由にした解雇や降格など不利益な扱いを禁じているものの、通報行為に対する刑事罰の免責規定はない。「通報者が逮捕される異例の事態。刑事裁判で公益通報を争点にした判例は見当たらない。正直、検討は難しい」と明かす。
通例ならば、不利益な扱いを受けた場合は民事訴訟で救済を求められる。しかし今回のケースは「制度の隙間に落ちてしまった」と日野教授は捉えている。「元生安部長の行為が公益通報と認められれば、刑法の『正当行為』として違法性を問われない可能性もある。いずれにせよ、今後の裁判は社会にとって重要な判例になる」と指摘する。