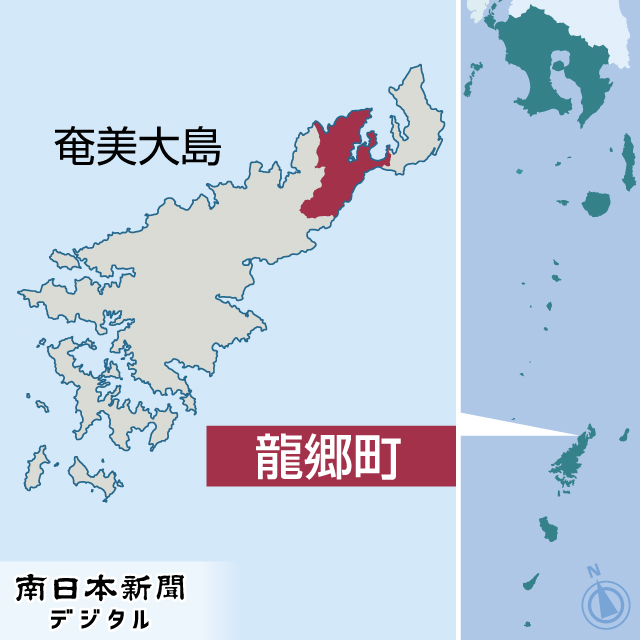救済待ち続ける民間人空襲被害者 戦後76年 見えぬ法制化に「死ぬのを待たれているようだ」 衆院選鹿児島
2021/10/28 20:41

「私の兄平田守利(生後6カ月)は、1945(昭和20)年5月9日の米軍の機銃で即死しています」。鹿児島市西陵8丁目の平田静也さん(72)は昨年9月、自民党の河村建夫元官房長官宛てに、故郷喜界島の空襲に関する冊子と手紙を送った。救済法の議員立法化を目指す超党派の「空襲議連」会長が河村氏だった。
元裁判所職員として「民間人も犠牲になった事実が葬られないよう、法律という公式な記録で残さなければ。後世への責任だ」と法制化を願う。被爆地広島選出の岸田文雄首相の就任は明るい材料と言い、「安倍、菅政権では無理だと思ったが、かすかな期待がある」と話す。
国は旧軍人・軍属に恩給や遺族年金を支払う一方、空襲で障害を負ったり、家族を失ったりした民間人への補償を拒否してきた。空襲議連は昨年10月、障害や精神疾患を負った生存者に限り1人50万円のみを支給する法案要綱を取りまとめ、政府に被害の実態調査も求めた。
ただ戦後補償の範囲拡大には慎重な意見もある。「とても同情するが、次々に補償を求める声が広がるのでは。国の財政状況も厳しい。再調査も時間がたちすぎた」。戦中の絵を描き、展示会を重ねる日置市東市来の野崎恭弘さん(85)は懐疑的な見方を示す。米戦闘機の機銃掃射、東の空が真っ赤に染まった鹿児島大空襲の光景…。恐怖体験が脳裏に焼き付き、「忘れちゃいけない」との思いは同じにもかかわらずだ。
全国空襲被害者連絡協議会は10月上旬、衆院選東京、大阪両選挙区の立候補予定者にアンケートを実施。新たに議連への参加意思を示した人もいて「会員を増やすことが大きな力になる」と捉える。
半世紀にわたって活動する薩摩川内市出身の安野輝子さん(82)=堺市=は「『今年こそは』と信じていただけに、法案も出されず絶望した。会長だった河村さんも引退し、置き去りにされた気分」と落胆を隠さない。
空襲で左脚の膝から下を失い、義足の装着部分が常に痛む。新型コロナウイルス下で外出できず、歩くのもままならなくなった。「周りは次々と逝く。国が始めた戦争の後始末をしてほしい。死ぬのを待たれているようだ」と吐露した。