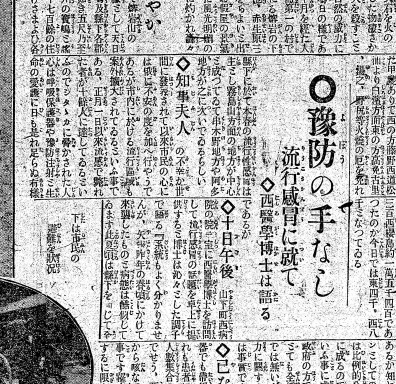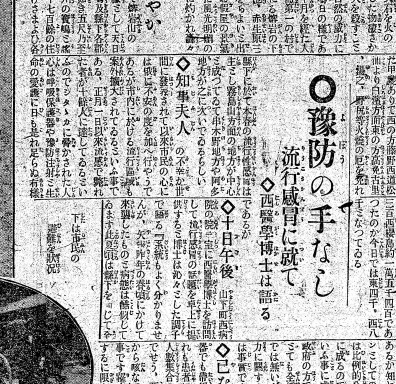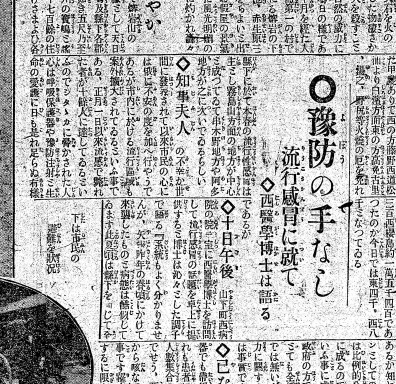
予防の難しさについて紹介する鹿児島新聞(1920年1月12日付)。鹿児島市の「西医学博士」は、「患者自身が公徳心から咳などの用心すること」の大切さを訴えている
〈忘れられた厄災・スペイン風邪 鹿児島の新聞から ④〉
未知の感染症への対策として当時さかんに奨励されたのが「呼吸保護器(マスク)」だった。鹿児島県の衛生課長が呼び掛ける。
保護器を使用せぬのは本県だけであるからこの際一般人がこれを使用する必要がある(1920年1月8日、鹿児島朝日新聞)
鹿児島ではよほど縁が薄かったとみえて、新聞も「マクス」と誤表記するほどだった。その“頼みの綱”も市民の元へはなかなか届かなかった。そば1杯7銭の頃に「買えば20~30銭もする」と、県はガーゼや針金を使った家庭での作り方を公表。弱みにつけ込む「マスク成金(なりきん)」もあらわれている。
日を追うごとに増える死者に、知事は危機感を覚えていた。10日には13項目の「感染予防心得」を発表し、人混み回避や換気、外出時のマスク使用などを切実に訴えた。このとき1日の死者数は鹿児島市だけで26人(19日)、東京では339人(13日)に上った。
マスク、うがいに並んで予防の柱だったのが「ワクチン」だ。
「ワクチン注射液が 5千人分来る」(同22日、鹿児島新聞)
当時のワクチンは細菌が原料で、ウイルス性肺炎には効かない。ただ肺炎を引き起こす細菌にも感染する患者もいたようで、肺炎球菌を加えた「混合ワクチン」などは有効だったかもしれない。市民も効果を疑問視しながら、すがるような思いで打ち続けた。ある者は「素人治療」を信じ、「蚯蚓(みみず)の汁」を飲んで命を落としてしまった。
医療支援もあった。死者が続出していた鶴田村紫尾には2月、済生会から鹿児島の医師が派遣され、1週間で130人を診療している。「流感患者以外」の患者も大勢が押し寄せたとあり、地方の医療事情の厳しさが読み取れる。
前年に多くの児童生徒を失った学校現場も、知恵を絞る。興味深いのが「予防のための事前休校」だ。鹿児島市の学校は、前年末から県内で拡大し始めた第2波が地方部から押し寄せる前に一斉休校していた。結果は集団感染を回避できたと評価できるものだったというが、問題も。教育現場を監督する視学の1人が語る。
生徒中にこの大切なる場合にも拘(かかわ)らず往々外出するを見受くるありこの如き行為は休業の趣旨に違背し且(か)つ自身の病毒を招来することともなるべきを以(もっ)てこの際出来得る限り外出せざるを得策とすべし (2月1日、鹿児島新聞)
地域組織もまた、社会防衛に必死だったのだろう。
「患家の軒に 赤布を提げて予防」(1月20日、鹿児島新聞)
日置郡伊作村では、警察分署長が衛生組長らを集め、患者のいる家庭を支援する一方で目印を付け監視を強めた。特定集落の交通を遮断したり、弔問を避けたりした所も。地域に分断をもたらしかねない状況が生まれつつあった。
「流感去って浴客賑(にぎわ)う」(3月3日、鹿児島新聞)
感染が「下火」になった20年2月。県民をあきれさせる“事件”が起きている。時機を逸した感染予防ポスターが内務省から「やっと届いた」のだった。それから約1カ月。一時は患者であふれた鶴田の紫尾温泉ににぎわいが戻りつつあった。
県境をまたいだ天草方面からの温泉客に、地元は「例年通り」と胸をなで下ろしたに違いない。
●このころ
鹿児島市は1920年、当時の伊敷村永吉や同村下伊敷の一部を編入し、人口が10万人を超えた。県の総人口は18年末時点で、145万9924人だった(内務省衛生局「流行性感冒」)。
箱根駅伝が誕生したのは20年2月14日。第1回大会に参加したのは早稲田、慶応など4大学で「4大校駅伝競走」と呼ばれた。5月には日本初のメーデー(当時は労働祭)が東京・上野公園などで開かれた。